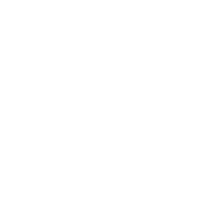王道にして、新章の幕開け。『Ephemeral』に刻まれたDIAURAの決意と愛情。この命の行き着ける場所まで届け――
去る1月18日、前ツアーファイナル兼14周年記念ライブを終え、活動15年目に突入したDIAURA。近年の意識の変化が、より明確にステージへと表れたツアーを経て、このたび彼らは新章の幕開けを告げるシングル作品を完成させた。「儚い」「短命な」などを意味する『Ephemeral』と名付けられた今作は、毛色の異なる全3曲で構成されながら、図らずも高い関連性を持つメッセージが込められ、DIAURAのあらゆる魅力を網羅した一作となった。
一人ひとりが変わりたいと思う気持ちの集合体がバンド(佳衣)

まずは1月の「The Holy Deringer」ツアーファイナル兼14周年記念ライブ「The“Dazzling”Deringer」を振り返りたいと思います。ライブレポに「DIAURAは今、何度目かの変革期を迎えている」と言い切り型で書きましたが、皆さん自身は現状をどう感じていますか?
yo-ka:自分で変革期と言い切るのは難しさがあるんですけど、ただ明らかに違うなと感じている部分はあって。どうしてもDIAURAって音楽を作る側とプレイヤー側で、多かれ少なかれ距離感はあったと思うんですけど、ここに来て、バンドとしての塊感をすごく感じられるというか。リハーサルをやっている時も、これまでで今が一番色々見えるようになったし、昔はどこか俺が歌ってりゃいいっていうところはありましたけど、皆で一緒に作っている感じが年々増していっているんですね。それが自分にとっても、DIAURAというバンドにとっても、健全な体質改善というか。そういうのを幾度か経てるような感じがしますね。
なるほど。
yo-ka:決め手はどこだったと言われると難しいですけど、気づいたら変わっていたみたいな、ドロドロの血がちょっとずつサラサラになったような感じがあります。だから、ちょっとずつ変わっていったというところを含めたら、きっとこの数年だと思うんですけど、ライブを作っていて、それが感覚としてわかるようになってきているし、そういう意識の問題なんじゃないかなと思います。意識が人を変えて、動かすから。今だったらこれをやってみたいなってことが、どんどん出てきている感じ。それを変化、変革だと言えばそうだと思うし。とにかく今、面白いですね。
ここ数年、バンドの贅肉を削ぎ落としたいと思っていて…という話も前回あって、それがあの日のライブで、これまで以上に明確化されたように思えました。
翔也:確かに、変わった感というのは自分自身としても実感しているし、お客さんから見ても、わかりやすく変わったところはあると思うんですよね。MCでも言いましたけど、これまで自分自身がどこか遠慮していた部分は確かにあったなっていう。メンバー各々やりたいことも違うだろうし、ライブの作り方も違うだろうけど、目指すゴールは一緒なんだから、その道筋が違ったとしても悪いことにはならないだろうと。だから我慢せずに、自分のやりたいことを押し殺さずにやってみようと思ったのは、ツアーが始まるぐらいの段階ですかね。新しいことをやるのは怖いっちゃ怖いんですけど、そこからやってみてダメだったらダメでいいやという考えにもなって。自分でケツ拭きゃいいしっていうところで、本当に誰にも遠慮しなくなりましたね。
「自分がカッコいいと思ったことだけを追求していく」と宣言していましたね。
翔也:そうですね。今ある環境って、すごく居心地はいいんですけど、それを壊してでもやりたいことが出てくるのはいいことだと思うし、やり続けないと成長もないだろうし。やっぱり意識は変わりましたね。
達也:年月を重ねていくごとに、自分はもっとこうしたほうがいいんだろうなという意識が、どんどん明確になってきたのと、ライブをやりながら3人に触発される部分もあって。お互いがお互いのカッコいいと思える部分を間近で見てきたので、負けたくない気持ちもありますし、ここ数年、一緒にステージを作って楽しめているんだなというのが、ライブの最中にもハッキリと感じられるようになりました。だから皆で一緒に、変化してきていると言われるステージが出来上がっているのかなとは思いますね。
佳衣:こうして14年やってきて、例えば4人で集まって改めて「よし、こう変わろう」って話はないんですけど、やっぱり一人ひとりが変わりたいと思う気持ちの集合体がバンドだし、それがバンドの良さなのかなと思うので、そういうタイミングは、あえて口に出さなくても訪れるものなんだろうなと。今がまさにそういうタイミングだったのかなと思いますね。
14周年のライブでも、「変わらずに変わっていこうと思います」と言っていましたよね。
佳衣:もう180度変わってやろうとかよりも、結局ここまでの年数やってきたら、自分って多分これしかできないなっていうところもあるので、それを続けていきたいし、ある意味での開き直りじゃないですけど、変わらずに、できることはこのまま貫き通していきたいなという気持ちはあります。だから、今までやってきたものも大事にしたいなとすごく思いますね。
あのツアーは全16公演中、ファイナルを含む8公演で「侵蝕」、あとの8公演で「ZERO」が1曲目を担っていたのもキーの一つだったと思います。1曲目は、オープニングSEとの親和性+ツアーの本筋が選曲のポイントなのかなと。
yo-ka:確かにそこは、先に決めていたポイントでしたね。「侵蝕」って、かなり前の曲(2017年発売のアルバム『VERSUS』収録)ですけど、頭の中でセットリストを組み立てながら、このツアーは「侵蝕」で始まるなと、パッと浮かんできて。どう考えても、自分の中ではその始まりだったんですよね。だから、佳衣がSEを作る時から、そこは割と固定化していくようなイメージと言っていました。短い曲ですけど、今言いたいことが全部入っていたんですよね。全然綺麗なことじゃないですけど、世の中や自分自身、相手を斜めから見ているような感覚で歌詞を書いた曲で。それをライブの頭で提示することが、『dazzle-消えた弾丸-』という作品と根っこの部分で通ずるものがあるなと思ったので。
まさにそれを感じました。ちなみに、オープニングSEは普段どのタイミングで制作しているんですか?
佳衣:毎回、リリースしてツアーが始まる直前、場合によっては1週間前の時もあります。ある程度セットリストも形になってきて、その世界観、雰囲気で見えたものをSEとして形にする感じなので、結構ギリギリが多いですね。
そうなんですね。あのツアーでは全公演でアンコール冒頭に各ソロセクションが入ったのも特徴の一つでしたが、手応えはいかがでしたか?
達也:普通だったら、本編とアンコールの間に一旦時間が空くじゃないですか。でも、僕が最初に出て行くので、Tシャツに着替えたらすぐに出る感じで、良い意味で本編のテンションがそのまま続いている感覚はありましたね。以前はアンコールになると気持ちが切り替わっていたんですよ。一区切りした安堵みたいな、緊張感がほぐれて表情も明るい場面が多くなるみたいなことが多かったんですけど、あのソロセクションをやることによって、良い緊張感が最後まで続いたというのはありますね。勢いづけるための爆発力のきっかけにもなれるように、色々考えました。
翔也:あれ、実は事前に打ち合わせをしたわけじゃなかったんですよ。ツアー初日のリハが終わってから、こういうのやってみない?って提案があって。だから、最初は本当にがむしゃらでした。ただ、自分がライブでこうしたいというものを、本編で提示するのももちろんですけど、その延長で、とにかくあのツアーは本当に汗をかきたかったんですよね。熱くなりたかったので、その感情のままにやっていました。熱量の交換というか、こっちがちゃんとやれば、応えてくれるんだなっていう信頼関係もできましたよね。
佳衣:ツアーが始まる前に、自分もちょっと思うところがあったので、その時に感じたものを反映させて、ツアーで面白いことができたらなとは思っていて。もちろん本編はバンドとして伝えたいものを全てぶつけるものだと思うんですけど、アンコールって、個々でお客さんに届くものをもっと出せるんじゃないかなと。本当に何の打ち合わせもなかったんですけど、とにかく自分が伝えたいものや、今表現したいものを出せる場所が、あのアンコールだったなと思います。結果、あの部分についての声もすごくたくさんもらいましたし、ちゃんと伝わったんだなと思いますね。
yo-kaさんは楽器隊3人の後、最後に登場する形でした。
yo-ka:今までにもヴォーカルがいないセクションを試みたことは度々あるんですけど、なんか定着しないというか。だからしばらくなかったんです。4人で演奏して曲を表現していく、世界観を作っていくのは当たり前の話で、ライブを作るという観点からいくと、もっとカッコいい、もっと痺れる場面ってあるだろうなと思っていて。俺が見たいのもあるし、愚民(ファンの呼称)に見てほしいのもあるし。各々が各々のポジションを背負っているわけだから、そこでもっと勝負できるんじゃないの?という思いがあって。それで今回、頑なに全公演であれをやったんですよね。あと、何が来たって打てよっていうところもありますし。翔也とか、ツアーをやりながらすごく変わっていくのがわかるわけですよ。楽屋にいても、聴こえてくる音でわかるし。
そうなんですね。
yo-ka:すごくいい機会だったなと思います。次のことを考えるなら、それこそ削ぎ落とせるものはまだあると思うし、フワッとしたところがよりなくなってガチッとなったら、端的にカッコよくなると思うんですよね。それができるということが見えたツアーだったなと。ヴォーカルが出て行ってヌルッと始まるのと、既に掴んだ状態で始まるのとでは、全然違うじゃないですか。それをもっと突き詰めて、もっとバンドにしたいなと思いますね。
では、今後のライブにも取り入れていきそうですね。
yo-ka:カッコよく見せられる武器ですからね。それは使わないともったいない。
絶対に終わりが来ることを受け入れたうえで、何を残せるか(yo-ka)

さて、14周年を迎えた=15年目に入ったわけで、今回のシングルはその第一弾作品という意識は制作段階であったのでしょうか?
佳衣:はい、まさに(笑)。
yo-ka:新章というか。今のこのメンタルのDIAURAだから、そうしたいと思ったんですけど、心機一転という言葉があるように、ここからまた始めようって気持ちは、いつ持ったっていいじゃないですか。でも、それってちゃんとそう思わない限りは、嘘っぱちなわけで。15周年を前にしてというのも一つのきっかけとしてはあるんですけど、またここで新たなスタートを切って、DIAURAを作っていこうよっていうところから、佳衣が「Ephemeral」を作る前に二人で話したのは、オープニングテーマだなということでした。でも、結構フワッとした会話だったよね(笑)。
佳衣:でも、そんな事細かに、ここをこうしてみたいな話がなくても、もうわかるもので、こういう感じだろうなっていう。で、自分自身もこうでありたいなという気持ちもあったので、それを本当にピンポイントで今回この曲に当てた感じですね。
「Ephemeral」は楽曲全体の印象として、温もりを感じるなと。
佳衣:温かさですよね。ざっくり言えば、イメージは割とストレートな感じというのはありました。でも、いろんな感情が入っているというか、ただ突き抜けて明るいだけじゃないし、そこにもちゃんと今まで作ってきたようにドラマ性、展開があってというのは意識しました。だから、これも一つの王道と言える、DIAURAの良さがすごく詰まった曲だなとは思います。
今作は3曲で一つという感覚が強いなと思って。必ずしも表題の曲名と作品名はイコールと限らない中、「儚い」「短命な」などを意味する『Ephemeral』が両方のタイトルであることもすごくしっくり来るなと。最初から統一したものを描こうとしたのでしょうか?
yo-ka:いや、最初に自分がc/w曲の「Optimal fiction」を作っていたんですけど、佳衣の曲はもちろんデモの段階では「Ephemeral」というタイトルもないので、世界観の統一を図ったわけでもないですし、「Ephemeral」に合わせて「Optimal fiction」に何か訂正を加えたとかもなくて。「Doomsday」に関しては、もう曲がそう言ってるんだっていう感じで書いたんですけど、確かに3曲とも不思議な関連性があって、自分でもこれは絶妙というか、やっぱりそうなるようになってんだなと、改めて歌詞を確認しながら思いましたね。
「Ephemeral」はDIAURAなりの決意と愛情表現とも受け取れるなと思いつつ、前回ちょうど翔也さんが「時間について最近色々考えるんですけど、生きている以上は残された時間というものがあるので、一瞬一瞬を大事にしていきたい」と話していて、今作と繋がるなと。
yo-ka:そういえば、そんなこと言っていたような気もするわ(笑)。
翔也:(笑)
これだけの年数やってきたからこそ、今、バンド内にそういう空気感があるのかなと思って。
yo-ka:こういう曲にしようと思ったことが、まずスタートでもあるので。結局、バンドにしても、一人の人間として考えても、終わりは絶対来るんですよね。なかなかにして目を逸らそうとするものですけど、今だからこそ、絶対に終わりが来ることを受け入れたうえで、何を残せるかってとこだと思うんですよね。そう考えた時に、じゃあそれをどう作品にメッセージとして残そうか、込めようかというところ一つでした。
前作『dazzle-消えた弾丸-』c/w曲の「SICKS」と共通の〈詩を敷き詰めて〉という歌詞が「Ephemeral」に含まれているのは、意図的なものでしょうか?
yo-ka :そこは意図的ですね。歌詞の内容としては「SICKS」と「Ephemeral」は全く反するところにありますけど、それも作詞の醍醐味というか。要は『dazzle-消えた弾丸-』を作った時に、次はなんとなくこんな作品がいいなみたいなのは、ぼんやりとあったんです。ただ、狙ってそこに当てに行くより、狙ってないのに当たるほうが快感というか。絞りすぎると、こぢんまりするんですよね。だから、あまり考えないで書いたんですけど、ここでこのはまり方はいいなと思いました。景色が違うだけで、やっぱり思いは近しいものがあるというか。これは作詞していて気持ちよかったですね。
サウンド面ではまず、冒頭と、その発展系の間奏の部分がとても印象的です。
佳衣:そんなに行き詰まることなく作れた曲なので、変に小細工をしなくてもいいだろうなという感じでした。だから、無駄なところは何のためらいもなく削ぎ落としていったので、そこまで頭を悩ませることなくできたんじゃないかなと思います。
Aメロ前には別のイントロが入るので、この曲はイントロが2パターンある形でしょうか?
佳衣:そうですね。最初にどういう曲にしようかみたいな段階で、絶対サビ始まりだろうなというのは頭にあって。そこを活かしたかったので、こういう形になりましたね。
そして、2B終わりからの展開がとてもドラマティックです。
佳衣:そこはDIAURAらしいなと自分でも思います。
達也:この曲はデモを聴いた段階で、構成が面白いなと感じたのと同時に、覚えるのがちょっと大変でしたね(笑)。Aメロ前のイントロは、あそこ1回しか来ないですし、サビの後に同じイントロが戻ってくるわけではなく、イントロ1が入り込んできたり、真ん中辺と最後の部分にキメの部分も入ってきたり、面白い構成だなと感じたのが印象に残っています。曲全体の雰囲気は疾走感がありつつ、切なかったり、儚さも入っているなと思っていたんですけど、歌詞と歌が乗っかったら、1本突き抜ける何かが見えたなと。そういういろんなイメージを踏まえて、ドラムの音作りも考えました。それと、スネアを連打して、止まってからバーンッといく、溜めて爆発させるような部分が結構あるので、そこも意識して演奏しましたね。
翔也:この曲は自分も王道だなと感じていて。今回、3曲それぞれで竿(ベース)を変えてみたんですよ。今まではメインで使っている1本で録ることもあったんですけど、王道の曲ならベースも王道でいきたいなと。で、ベースといえばフェンダーだろ、その音作りで使うエフェクターはこれだろみたいなのがあって、それでやってみたらやっぱり想像通りというか、大分イメージに近づけたかなと思いましたね。