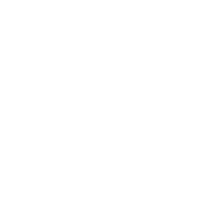実験的音楽による常識の破壊。THE MICRO HEAD 4N’Sによる新プロジェクトOFIAM、待望の初音源『棘』が遂に世に放たれる――。
今年5月末に第三期の活動を終え、ヴォーカル不在となったTHE MICRO HEAD 4N’Sが、バンド本体とは別に新たに始動させたプロジェクトの一つが“OFIAM”。逆から読めば“MAIFO”(マイフォ)である通り、あくまでTHE MICRO HEAD 4N’Sへ帰結するため、「実験的音楽による常識の破壊」をテーマに自らの進化を求める。ギタリストkazuya、SHUN.、ベーシストZEROによるプロジェクトでありながら、全員がVoiceという肩書きを併せ持ち、歌や語りも素材の一つとして扱いつつ、さらに映像も駆使しながら表現していくのが彼らのスタイルだ。そんな他に類を見ないOFIAMの始動からこれまでのこと、待望の初音源となる1stシングル『棘』についてじっくりと話を聞いた。
“世の中の普通”をひっくり返すことが面白い(kazuya)

今年6月に、THE MICRO HEAD 4N’S Still NightとOFIAMの始動が発表されました。始動の経緯は、8月21日に行われたTHE MICRO HEAD 4N’S10周年&OFIAMの1stライブのレポートを読者の方にぜひ読んでいただきたいですが、マイフォの活動を止めたくないというのが一番大きな部分ですよね。
kazuya:そうですね。前ヴォーカルとお互い一緒にやっていくことが難しいよねと決まった時に、これからどうするかということをメンバーと話していて。メンバーの意思としては継続と、止まりたくないというのがあったので、この二つを僕なりに考えた時に、まず新しいメンバーをすぐに見つけるのは正直難しいなと思ったんですよね。でも、活動を止めたくないと。4人の結束力はすごいなと思ったので、これらを考えるとやっぱりこうなるというか。その上で、過去に自分が考えていた色々なこと、KREUZ(THE MICRO HEAD 4N’S内のインストゥルメンタルプロジェクト)の発展系、そういう活動形式としてStill Night、OFIAMを作りました。
マイフォに新ヴォーカルが見つかったとしても、三つのプロジェクトを動かすと決めているということで、その意思表示の一つとしてOFIAMの音源をガツガツ作っていくと。実はもうアルバムを出せる曲数が存在していますよね。
kazuya:ありますね。去年にはもう「棘」の原型はあって、実験台として演っていたんですよね。自分たち自身のことなので、バンドがこういう状況になるのは活動していく中で段々と予測できるわけじゃないですか。なので、急ピッチにアレンジを進めて、何曲か既にレコーディングしていました。それがあったので、結構曲数ができていて。結果、それとは違う曲が今回シングルに入ってきたんですけど(笑)。レコーディング自体は結構楽だった気がします。それよりも、この世に見本みたいな人がいるバンドではないので、とにかく自分と向き合うしかなくて、細かいアレンジにすごく気を使いましたね。正直マイフォとか比じゃないレベルで。マイフォだと、5人組バンド、ロック、歌モノ、ヴィジュアル系とか、お手本になる方々がいっぱいいるし、僕もそういう中で生きてきたから、こうすればいいというゴールが見えているんですよ。だけど今回はゴールがわかりづらいというか、自分で考えないといけないから、すごく時間がかかりました。
OFIAMは「実験的音楽による常識の破壊」をテーマに掲げていますが、6月の発表時に、「世の中の常識は非常識、非常識は常識であることを証明したい」とkazuyaさんが言っていましたよね。ヴォーカルが脱退したらバンドは終わりみたいな風潮を覆したいと。
kazuya:まさに、それのみです。そういうの面白くないすか?っていう世の中への提示というか。やっぱり噂話とかで、「マイフォ、またヴォーカルが抜けて云々」みたいなのって普通に出ると思うんですよ。でも、こんな形で活動するなんて、誰も想像が付かないだろうという。それも踏まえてエンターテインメントなのかなと。僕的には、僕らの生き方を踏まえたエンターテインメントをファンの方々に楽しんでもらいたいと思っているので、望まれた未来かどうかはわからないですけど、あのまま解散という“世の中の普通”をひっくり返すことが面白いのかなと。あと、昔よく「バンドを作ったんです」という後輩に「じゃあ早くライブやりなよ」って言うと、「でも、ベースがいないんです」とか「ギターがいないんです」と言う子が多くて。そんなの別によくね? やっちゃえばいいじゃんって思っちゃうんですよ。行動した人にしか未来はないので。そういう意味では、こうやって必死に生きている姿は多少面白いと思ってもらえるんじゃないですかね。
皆さん逆境に燃えるタイプですか?
ZERO:そうですね。例えば俺のことを嫌いな奴がいたとしたら、そいつを見返してやるというのが俺の性格上の常だったので。ライブとかでも、結構アウェイのほうが強いんですよね。そのほうが燃えるし。今回のOFIAMのことで言うと、マイフォは過去に3人ヴォーカルがいて、脱退、加入というので成り立ってきたバンドなので、そこで4人の底力が実証されていると思うんですよ。だったらこの4人でやってみるのが、一つの新しい可能性を広げる手なのかなと。
SHUN.:僕は…普段は逆境に萎えるタイプなんですけど…。
ZERO:ウサギの心臓ですからね(笑)。
kazuya:ハートがすこぶる弱いので(笑)。
SHUN.:ただ、色々な意味で耐性が付いていますよね。今の状況ももちろんですけど、仕事一つとっても、そういうことは誰にでもあることだと思うんですよ。人よりもちょっと多いとは思うんですけど。まぁだから…逆境には萎えるタイプですけど、慣れているので何とかなっています(笑)。
0から1を作ることの難しさと楽しさがあると思いますが、6月の発表時までに色々仕込んでいる期間が一番大変だったんじゃないかなと。
kazuya:ヤーキーズ・ドットソンの法則というのがあって。いわゆる、ちょっとピンチになっている時のほうが人の才能が出やすいという法則で。例えば僕が1週間自由で「曲を作って」と言われても、ひたすらボーッとしちゃうと思うんですよね。でも、バンドが止まっちゃうかもしれない、次の展開を作らなくちゃいけない…あーっていうストレスがあるじゃないですか。そのストレスを良い位置で持っていれば、才能って通常よりも出るらしくて。この1年はまさにそれだったと思うんですよ。「あー、終わってまうー。次作らないとー。Still Nightもやりたいー。あーーー」って。ずっと「あー」って言っているまま1年終わりそうな感じというか(笑)。
(笑)
kazuya:でも、お陰様で曲はめちゃめちゃできるし、何も困ることはなくて。もちろん、ロールモデルがないというところで、基準を作るのは難しいなと思います。例えば自分が別に歌が得意でもないのに、モドキみたいなことをすることに対して大丈夫なのかなとか、そういうことは考えたりしますけどね。
OFIAMの最初のアー写が解禁になった時、率直にカッコいい!という印象で。外ロケも新鮮でしたし、アーティスティックな写真だなと。ZEROさんの発案でしたよね。
ZERO:音楽が割とデジタルなものなので、それと対極なものを出したいという部分で、自然と機械的なものの融合ということと、音楽を身に纏っているので、ヴィジュアル面ではシンプルに見せたかったというのがありましたね。砂漠で撮ってみたかったというのもありますし。あの場所は海もあったので、本当はそっちでも撮りたかったんですよね。トレーラー映像に使っている「命」という曲があるんですけど、イメージ的には砂漠と海で、生命が生まれて生命が還る場所というか。そういうものを一発目で出したったんです。
映像を一つのメンバーのように捉えてもいいのかなと(SHUN.)

OFIAMはこれまでに2本のライブを行いましたが、オープニング映像の中に、アインシュタインの名言でもある「In the middle of difficulty lies opportunity.」(困難の中にチャンスがある)という言葉があって。始動ライブ用のものかと思っていたのですが、ツーマンの時にもあったので、やっぱりこれがOFIAMの根源なんだろうなと改めて思いました。
SHUN.:OFIAMって結構特殊なバンドなので、歌ではない言葉として伝えるのも面白いなと思っていて。SEでも、音の中に言葉はなくても映像にそういうものを入れることによって、そこでもOFIAMを表したいなというのがあったので、英語ではありましたけど入れました。ツーマンの時はちょっと変えたりもしたんですけどね。1回目の時は、確か「全てはここから始まる」というようなことも入れていて。
「A new story started. Believe in yourself. Change the world.」とありましたね。
SHUN.:ツーマンの時は、2回目のライブなのでそこを変えたりして。そういうメンバーもあまり気付かないようなところをマイナーチェンジしたり、映像も僕は力を入れていますね。
OFIAMの表現方法は映像も必須というところで、担当しているSHUN.さんは相当大変だろうなと。
SHUN.:ライブハウスの環境とか色々と関係してくるので、今後どうなっていくかわからないですけどね。ただ、プロジェクターにちょっと流すくらいはマイフォでも演出の一環としてやっていたんですけど、OFIAMは可能な限り曲中に流せるものは流したいなと思っていて、視覚的にもメッセージを届けられたらと思っています。あと、ヴォーカルという一つのピースがない分、代わりにビジョン的なもので表現できたらというのがあったので、変な言い方ですけど、映像を一つのメンバーのように捉えてもいいのかなと僕は思っていますね。
初ライブはとても独特の雰囲気でしたが、振り返ってみていかがですか。
kazuya:めちゃくちゃ独特でしたよね(笑)。ファンの方々が途中まで座っていて。ただ冷静に考えると、OFIAMを立ち上げた時のテーマの一つとして、コロナ禍というのもあったから映画のように観られるバンドも良いのかなというところで映像も入れていたりするので、そういう風に楽しんでもらうのもアリかもなという感じではあるんですけど、ああいう状況が自分たちは初めてで、しかも初ライブだし、最初はちょっと「うっ」とは思いました(笑)。でも、ちゃんと曲の世界に入れて、最後はハッピーに終われたかなと。何でもそうですけど、新しいことを始められるというのは幸せなことだなと思います。
ZERO:僕、初めてイヤモニを使用したライブだったんですけど、結構そっちが手いっぱいで(苦笑)。ライブをやった感じとしては、コロナというものがなくなって、自由にファンの方も参加できるようになった時に、このライブの醍醐味がきっと5倍くらいになると思うんです。今の状態でも成り立つとは思うんですけど、何の制限もなくなった時に多分すごい現象が起こると思うんですよね。それを想像して楽しみながらやっていましたね。
SHUN.:僕はいつもの3倍緊張していました。そして、いつもの3倍記憶がないです。
ZERO:直前まで映像の作業をやっていたから、ライブ中寝てたんじゃないすか(笑)?
kazuya:そういえば今までライブ中に寝たことはないよね。
SHUN.:寝たらあかんでしょ(笑)。
ZERO:眠くてライブやって、ぶっ飛びがいつもよりぶっ飛んでいることありますよね。
kazuya:俺、それオールナイトの時にあった。何回か記憶がないわ。
ZERO:始まった直後と、終わった時の記憶しかないことがたまにあるんですよね。
SHUN.:僕はそんな感じでした。めちゃめちゃ緊張しましたね。
2回目のライブが10月23日に行われた夜-yoru-とのツーマンでしたが、曲数も初ライブより1曲多かったですし、MCもたっぷりあってワンマンのようなライブだったなと。そして演奏とMCのギャップがすごいなと思って(笑)。OFIAMはMCもカッコよくキメようという話があったようですが…早々に諦めたのかなと(笑)。
全員:(笑)
ZERO:あの日に関して言ったら、MCでサポートの人(TSUKASA)に話を振ったのが悪かったですね(笑)。
kazuya、SHUN.:確かに(笑)。
ZERO:あそこから狂っていったんですよね(笑)。
kazuya:でも確かにセットリストは、あの時出せる全曲だったんですよね。なおかつMCも全員回したという(笑)。対バンのファンの方々に非常に申し訳ないことをしました(笑)。
ZERO:まぁでも、1回目よりもうちょっと砕けたほうがいいなとは思ったんですよ。ただ、あの時はちょっとやり過ぎかなと思いましたね(笑)。
kazuya:今後はその真ん中を狙います(笑)。
ZERO:やっぱりマイフォありきでOFIAMのライブに来ている人がほとんどだと思うので、あまりギャップを作ってしまわないように、観に来てくれたファンの人たちに対して充実感を残さないといけないと思っているんですよね。なので、今後マイフォが復活して、OFIAMは別で活動していくとなった時には、完全に分ければいいと思うんです。本来だったらOFIAMは初ライブの時のような形がいいと思うんですけど、今は本体が動けないので、ある程度歩み寄りが必要なのかなという気はしています。
ちなみに、ツーマンで1曲、和登さん(夜-yoru-)がゲストヴォーカルで参加したのにはビックリしました。それもアリなのか!いや確かにアリだよなと思って。本当に無限の可能性があるプロジェクトだなと。今後も色々なコラボレーションをしていく可能性はあるのでしょうか?
kazuya:そうですね。ヴィジュアル系初のインストバンドとして、ヴィジュアル系界のスカパラじゃないですけど、いろんな方々とやれたら面白いかなと。それは僕らも楽しいし、世の中にとっても楽しいことかなと思っていて。近い未来そういうことはやりたいなと思っています。
これまでライブで9曲披露済みですが、1stシングル表題曲の「棘」は、まだOFIAMが存在していなかった1年前の配信ライブで原型を初披露していたので、1年越しのリリースとなります。初音源は絶対にこの曲と決めていたのでしょうか?
ZERO:OFIAMの初ライブの前に、YouTubeで試聴会をしたじゃないですか。そのあと、昔関わっていたスタッフとかが急に電話してきたんですよ。「マジでカッコいいよ」と、すごく高評価で。その中でも最初に「棘」が「すげーカッコいい」と。関係者や友だち、元メンバーからもそういう言葉を聞いて。テーマ性も含めてですけど、そういう評価を考えた時に「棘」は最初に世に出すべきものなのかなと思いました。
ある意味このプロジェクトの始まりの曲でもある「棘」が1stシングルになるというのは、すごく綺麗な流れでもあります。
ZERO:普通であれば、バンドって歌モノを前に出したくなりますけど、このバンドはそうではないので、インストがメインでもいいと思いますし、声が入っていても入っていなくてもいいんですよね。その中でもメッセージ性がある「棘」が一番なのかなという感じですね。
kazuyaさんが「人生で一番苦労した曲だと思う」とインスタライブで話していましたが、その一番の要因というのは?
kazuya:僕は、曲は無限に書けるんですよ。それはあくまでメロディーというロールモデルが世の中にあるものだから。でも、これってロールモデルがないから自分でOKを出さないといけないわけで、無限にOKが出せないんですよね。そんな悩んでいた時に、EDMとかで使われているヴォーカルチョップというものに出会って、これは利用できるんじゃないかなと思ったんです。なぜかと言うと、EDM系を聴いていると、メロディーがある印象が頭に残るんですけど、実は歌っていないものが結構多くて、要は声を切って切ってメロディーを作っているんですよね。それをやってみるかと。そこからサンプリング系をダーッと勉強して、「棘」のサビの最初の〈ハーアア〉という部分を入れた瞬間にコレキタ!となって、そこから一気にアレンジが完成していきました。あの出会いがなかったら、まだフワフワしていたかもしれない(笑)。何をすればいいかが見つかったというか。ヴォーカルはいないんだけど、その代わりになる人を何万人も持っているような状況なんだと。今年の中でもあの発見は大きかったですね。しかもそれを自分でコントロールできるようになってきているという。
SHUN.さんの発案で語りを入れることになったそうですが、それはどの段階で思い付いたのでしょうか。
SHUN.:kazuya君からデモを聴かせてもらって、あと何か必要なピースがあるのかなと考えたんですよね。マイフォで間奏に語りを入れたのは1~2曲あって、それまでは個人的にもマイフォとしてもやったことがないことだったので正直抵抗があったんですけど、入れた時にピッタリはまったんです。今回も、例えばもっと違う音を足すとか、いろんな方法があると思うんですけど、メロディーではない声というものがあったほうが面白いのかなと。それで試しに語りを入れてみたら、「あ、良いんじゃないか」と。ただ、語りってすごくダイレクトに伝わりやすいなと思っていて、そこは歌詞を書く時に少しデリケートになったところでもあります。逆にメリットとしては、メロディーがないので文字数を全く気にしなくていいのがすごく嬉しかったですね(笑)。
kazuya:その分、歌詞カードが酷いことになっとるやん(笑)。
SHUN.:そう、気にしなかったらめちゃめちゃ多くなって(笑)。メロディーがあると、どうしてもそこに文字を当てはめたり、母音一つとっても、このメロディーに「あ」の母音はちょっと違うなとかあったりするんですけど、そこの制限がなかったので、好きなことをガッと…ん?あれは好きなことではないな(笑)。思ったことを…。
ZERO:SHUN.さんの心の闇を思う存分表現できたと(笑)。
闇が深い詞だなと思いましたよ(笑)。
全員:(笑)
kazuya:明るく振舞っている人こそ、実は一番闇深かったりするもんですよね(笑)。
SHUN.:(笑)。でも、皆こういうことないっすか? 誰かに言われたことだったり、自分で言ったことでも、すごく気になってずーっと刺さっているという。ただ、最終的にはラブソング的な感じにはしてあるんですけど。
最後の部分は1年前にはなかったですよね。
SHUN.:なかったんですよ! よくご存知で!
なぜあの部分を入れようと?
SHUN.:あれを入れると印象は変わると思うんですけど、元々ああいう意味合いだったんですよ。あえてその言葉を入れていなかっただけなんです。元々ラブソング的に書いたつもりだったんですけど、そうは見せたくなくて。でも僕、大どんでん返しみたいな映画がすごく好きで、最後の一言で歌詞の意味が「あ、そっち?」ってなるのも面白いかなと。最後に一言付け加えることによって、見え方が変わるのも良いかなと思ったんですよね。他にもちょいちょい変えたと思うんですけど。
大枠の意味合いは変わってないですが、言い回しが所々変わっていますね。
SHUN.:そうですよね。1stライブの時からも変わっていると思います。映像にテロップが乗っているんですけど、今作業していたら、ちょっと歌詞が違うなという部分があったので、微妙な変化はあったみたいです。自分のことなのに覚えてないですけど(笑)。