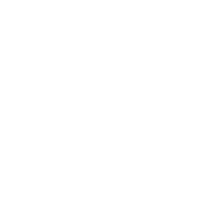2017.7.15
sads@名古屋・ReNY limited
『try out a new blade』
7月のライブ開催が恒例となっているsads。今年ももちろん例外ではなく、7月15日の名古屋・ReNY limited公演を皮切りに『try out a new blade』と銘打たれた東名阪ツアーがスタートしている。去る4月、新メンバーにYUTARO(b)を迎えている彼らだが、その新布陣でのフル・サイズのライヴは今回が初となる。それだけにファンからの注目度の高さも並大抵のものではなく、この日の公演チケットはあらかじめ完全ソールド・アウトとなり、立錐の余地もないほどぎっしりと人で埋め尽くされたフロアは開演前から熱気が充満した状態。午後6時14分、場内が暗転し、オープニング・チューンの「HONEY」が炸裂すると、それまで堰き止められていた熱が一気に放流され、その場はまさに灼熱地獄ならぬ激熱天国と化した。
sadsのライブは、普通の感覚で言うところの緩急に富んだものではない。緩やかな場面が存在するとすれば、それは曲間のお喋りくらいのもの。基本的には、激しいものとより激しいもの、強烈なものともっと強烈なものによるコントラストにより、まさに禁断レベルといえるほどの興奮がもたらされることになるのだ。この日のライブも当然ながら、それは同じこと。あくまでK-A-Z(G)とGO(Dr)の超獣コンビをサウンド面での軸とする体制となった2010年以降の楽曲群主体に組まれた演奏プログラムから感じられるのは、それ以前のsadsとも、いわゆる今日的ラウド・ロックとも種類の異なる激烈さ。矛盾して聞こえるかもしれないが、ささくれだっているのに成熟感があり、凶悪な爆音でありながらすべてが理に適っているから聴いていて心地好いのだ。そして当然ながらそうした図式は、いかなる楽曲であろうと自分なりの着こなし方で支配してしまうことのできる、清春という唯一無二のカリスマの存在があってこそ成立し得ているものでもある。
この夜のライブでもそうした清春の特異さ、現在のsadsのバンドとしてのポテンシャルと機能性の高さを感じずにはいられなかった。しかも清春は、発する声ひとつでその場の空気の色を変えてしまう術を身に付けている。たとえば彼には、YUTAROが長く籍を置いてきたゼリ→のデビュー・アルバムのプロデュースを手掛けてきた過去があり、説明せずともそうした背景を知り尽くしたオーディエンスの前で「まさかYUTARO君と一緒にバンドをやるとはね。超イヤです」などと愛ある絶妙なジョークを吐いてみせたりもする。さらには、この夜のライブに清春自身の母親が来場しているという、普通ならロックスターが敬遠しがちな和やかな話題も躊躇なく提供してしまう。が、そうした言葉でフロアに張り詰めた空気を緩めた直後、「名古屋!」という叫びひとつで瞬時にしてオーディエンスを束ね、その場を急速加熱させてしまうのだ。
この夜も、清春のそうした手腕は存分に発揮されていた。が、場内に渦巻く熱のすさまじさは、いつのまにか彼自身の想定の範囲を超えるものになっていたのかもしれない。事件は、最後の最後に起きた。二度目のアンコールに応えて「THANK YOU」が披露された際、お立ち台の上から客席を威圧していたはずの彼の姿が、崩れ落ちるように視界から消えたのだ。そして同楽曲が終わると、そのまま彼はステージから引き揚げていく。興奮の余韻に不穏な空気が入り混じるなか、観客の何割かは会場出口へと向かい始める。が、そこで聞こえてきたのはK-A-Zの「やるぞ! 戻ってこい!」という言葉だった。続けざまに耳に飛び込んできたのは、清春の「名古屋! 突っ込め突っ込め!」という扇動。やはり、これを聴くことなしには終われない。炸裂したのは、言うまでもなく「CRACKER’S BABY」だ。しかも清春は、椅子に座った状態で歌っている。この光景には、その場に居合わせた誰もが驚かされたはずだが、どうやら彼はお立ち台を降りる際にバランスを崩し、不自然な体制で着地したことで突発的な痛みをおぼえ、立って歌うことがままならない状態に陥っていたようだ。ただ、座ったままでも鋭い眼光ひとつで威嚇し、場を支配してしまうことができてしまうのが清春という男。実際、着席状態のまま歌われても、この曲の過激な攻撃性が損なわれてしまうようなことは一切なかった。そんな彼のまさにカリスマたる所以と、ステージに賭ける思いのすさまじさを、筆者は改めて痛感させられた次第だ。
こうしてゴール付近で波乱の場面を迎えたツアー初日だったが、公演終了後、清春はインスタグラムを通じて「名古屋ありがとう。皆さん僕は大丈夫、一旦始まったライブは最終的には絶対なんとかしますんで心配なんてしないでください」とメッセージを発信しており、どうやらステージ終盤での負傷は大事には至らず、名古屋を後にする頃には痛みも消えていたとのこと。もちろん、この先に控えている東京、大阪での公演にも支障はないという。また、そもそも今回のライブはYUTAROを擁する新ラインナップの切れ味が試される場でもあったはずだが、そうしたテーマはいつのまにか筆者の意識からは抜け落ちていた。それは、誤解を恐れずに言えば、まるでずっと前からsadsがこの顔ぶれだったと思わせるようなナチュラルさ、必然性の伴ったフィット感がライブ自体から感じられたからこそでもあるだろう。
そして、もうひとつ重要なことをお伝えしておく。前述のアクシデントが発生する少し前、清春がステージ上で発したのは「来年はsadsのニュー・アルバムを作りたいと思ってます」という、その場にいた誰もがいちばん求めていたはずの言葉だった。実際のところ現時点においては具体的なリリース日程が決まっているわけではなく、今回の東名阪ツアーの先にも具体的なライブ予定があるわけではないようだが、2010年7月7日に世に放たれた『THE 7 DEADLY SINS』の〈7周年イヤー〉の着地点にあたる2018年夏までの間に、ファンが長らく待ち続けていたことが叶えられていくことになるに違いない。そんなsadsの今後を占ううえでも、間近に迫りつつある東京、大阪での各公演を絶対に見逃さずにおきたいところだ。
(文・増田勇一)