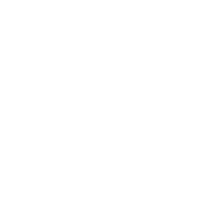結成30周年を迎えたPlastic Treeがバンド名を冠したアルバムを発表。全てのプラらしさが表現された待望の最新作を紐解く
ライブ活動をバンドの中心に据えてきた3年余を経て、Plastic Treeが作品作りを再開させたのが2023年。そして2024年、結成30周年を迎えた彼らが、満を持してバンド名を冠した新作アルバム『Plastic Tree』を世に送り出す。メンバー4人が2曲ずつ作詞作曲を手掛けた新曲8曲に、2023年発表のシングル曲を加えた全10曲収録の今作は、4人の個性が色濃く表れ、それはすなわち「全てのプラらしさを1曲1曲が体現している」作品となった。4人揃っての登場は約4年ぶりとなるPlastic Treeに、30周年を迎えた現在の思いと待望の最新作についてじっくり話を聞いた。
バンド名のタイトルを付けるのは今このタイミングなんじゃないのかなと(有村竜太朗)

30周年おめでとうございます!
全員:ありがとうございます!
30周年を迎えた実感はありますか?
有村竜太朗(以下、竜太朗):あるっちゃあるけど、嘘でしょ?って感じもあります(笑)。「30年も経ったんだ」という方が強くて、客観的に考えると、えらい時間やらせてもらっているんだなと。
20周年の時と30周年では、感覚の違いはありますか?
長谷川正(以下、正):我ながらというか我々ながら、20年でも十分すごいなと思ったんですけど、やっぱり30周年になると、さらにすごいですもんね。バンドとしてこれだけやって来られたというのは、幸せなことだなと改めて思いますね。
ナカヤマアキラ(以下、アキラ):20周年と30周年では、感覚は全然違うね。20年の時は「やったなぁ」で、30年は「そうなんだ? すごいな」みたいな(笑)。どの方面に対してすごいという気持ちがあるのかは、応援してくれた人たちもそうだし、やっぱり僕らもそうで。20周年の時はもうちょっと気楽に祝っていたような気がするけど、30年…スッゲーなと思いますよね。
佐藤ケンケン(以下、ケンケン):10年前って、どんな頃でしたっけ…?
20周年の2014年はミニアルバム『echo』(3月)、シングル『マイム』(9月)をリリースしていますね。
ケンケン:その頃、俺が加入してまだ5年くらいってことですもんね。がむしゃら感とか考え方みたいなのは、10年前と今では個人的には多分変わっていると思うんですけど、何が何でも継続させるぞみたいな感覚は、その時もあまりなかったのかなという気がしているんですよね。そこは今も変わらないかなと。活動は全部精一杯やっているんですけど、続けることに関してはそこまで意識してないし、メンバーからも良い意味で感じられないというか。踏ん張って継続するということではなく、自然に今になっているみたいな。
継続することが目的ではないですもんね。
ケンケン:そうそう。ただ、バンドって本来めちゃめちゃ脆いものだと思うんですよね。俺も20代の頃にバンドの解散を経験してきて、簡単なことで壊れるのはわかっているし。でも、プラの場合は意気込んだりせずに、ナチュラルにニュートラルに続けられているのがすごいなと思いますね。
竜太朗:この10年の時代性もあったと思うんですけど、やっぱり僕も20周年の時とは随分感覚が違いますね。自分の年齢や世代的なこともあるし、自分がやってきたことに対して客観性も持ちますしね。色々思うところはあります。でも、一言で言えば、すごく嬉しいことだなと思います。極端な話、誰かが体を壊したらできないじゃないですか。そういうのもひっくるめて、メンバー皆元気にライブができて、物を作れているって、この20周年から30周年も幸せな10年間だったんじゃないかなと思います。
この度、30周年“樹念”アルバム『Plastic Tree』が完成を迎えました。まず、少なからず驚きがあった、このタイトルに決まった経緯を教えてください。
竜太朗:理由がいくつかあるんですけど、一つは30周年という節目に出す作品だというのが、まず根底にあって。それと同時に、自分ではなかなか不思議なバンドだよなと思っていて、なんとなく付けたこのバンド名そのものをアルバムタイトルにして作品を出すのも、いずれはやりたいなと昔から思っていたんですよね。
そうだったんですね。
竜太朗:30年前からずっと、物を作ってツアーをやるというのをルーティーン的にやってきたんですけど、コロナ禍だったりで、ちょっとそれが途絶えちゃったわけですよね。その時、僕たちはメインになる活動として生配信ライブ「Peep Plastic Partition」をやってきましたけど、ただ楽しいからやろうみたいな感覚じゃなくて、新しい表現としてそういうものをやってみたくて、そこで過去の作品に触れることも多くて。それで一度、作品作りから離れていた時期もありましたけど、バンドのモチベーションを下げずにやってきて、今度はまた新しい作品作りもやろうと再開した時に、バンド名のタイトルを付けるのは今このタイミングなんじゃないのかなと。また0ベースに戻っているような感覚もあったので。
なるほど。
竜太朗:これは僕だけかもしれないですけど、曲作りや歌詞の書き方とか忘れちゃったなみたいな感覚もちょこっとあったり。でもそれってバンドを始めたばかりの時に「歌詞とは? 曲とは? うーん」ってなっていた自分も思い出したし、色々なことが1回また巡ったなみたいな感覚もあって。ただ、皆でアルバムを作っている間に誰かから他のテーマが出たら、それはそれだしと思って一意見として考えていたんですけど、皆から出てきたデモだったり、全員でプリプロをやっているうちに、やっぱり今回は『Plastic Tree』なんじゃないのかなと。段々と決めていった感じですね。
正:実際に作業を進めていって、ちゃんとどの曲も今の自分たちが表現できているし、『Plastic Tree』と冠していい内容のアルバムじゃないかなと感じました。このバンドの30周年はもちろん今しかないので、そういうタイミングで、このタイトルを付けてもいいと思える内容の作品が作れたのは良かったなと。さすがにこの内容だったら違うタイトルの方がいいんじゃない?ってこともあり得るわけですけど、そうではなくて、ちゃんと内容にも沿っているし、30周年というタイミングもやっぱり大きかったなと。
今作にも収録されているシングル『痣花』(2023年7月発売)が3年4ヵ月ぶりの新曲で、竜太朗さんと正さんはコロナ禍になってからそれまでの間、あまり曲作りをする気持ちになれなかったと話していましたよね。アキラさんとケンケンさんはいかがでしたか?
アキラ:俺はどっちでもないかな。曲の原案なんてものはどうとでも作れるけど、バンドとして物を作るというのは、メンバーの誰かが今やれないってなったら、やらなくていいんじゃん?と思ってたの。ただ、「あえて言うよ。俺は作りたい」とは言っていたんです。そういう意見交換はずっとしていて。でも、集団としてそこまで義務である必要はないかなと。もしビクターさんから「いや、出してください」と言われたら、話し合い直さなきゃいけなかったけど(笑)。あの時期は皆、何をしていいかわからない状態だったから、この人たちだけは頑張ってくださいとは言えないよね。自分も含めてね。
ケンケン:俺は、モチベーションは多分下がっていたと思いますね。活動的に音源ももちろん大事ですけど、ライブの存在がやっぱり一番大きくて、それが一度なくなっちゃったので、どうしたらいいんだろうなっていうのはありましたよね。でも制作物って、締め切りがあるから作れるみたいなところはあると思うので、そこは大きいかなと思います。ただ、配信ライブをずっとやっていたのは本当に大きいことだったなと、今も思いますね。
『痣花』のインタビュー時に「やっと制作モードになってきている」と話していたので、その後、具体的にアルバムの曲作りが始まっていったのでしょうか?
竜太朗:各々曲も作っていっただろうし、『痣花』の時くらいから状況も気持ちも整ったってとこじゃないですかね。リリース計画も具体的になってきたし、ライブをする環境も少しずつ規制が緩和されていって、また状況が変わりつつあるのかなという感じになっていたので。で、配信ライブとかでバンド活動は止めていなかったので、単純にもうそろそろ物を作りたいなという、制作欲求みたいなのが高まったんじゃないかなと思います。
近年のアルバム作品で言うと、正さんが以前、『doorAdore』(2018年3月発売)は重厚感という方向のプラらしさの表現を突き詰められたと思っていて、『十色定理』(2020年3月発売)は『doorAdore』とはまた違うキャラクターの作品で、風通しの良さが一つの特徴のような気がしていると話していましたが、今作の全体像はどのように感じていますか?
正:作品自体のボリューム感とか、メンバーがそれぞれ2曲ずつ作詞作曲をするという、アルバムの構造って言うのかな。そういうフォーマットは『十色定理』の時にすごくいいなと思ったので、踏襲していて。それプラス『doorAdore』に近い重厚さもあるし、そういうのも踏まえて、自分たちが辿って来た中でこれはいいなと思えるものが、今回ちゃんと全部取り入れることができたんじゃないですかね。
今作の新曲たちは、詞曲の作者を一緒にする前提で曲作りを始めたのでしょうか?
竜太朗:いや、決め事ではないです。基本そうだけど、何か希望があれば言うみたいなルールな気がして。でも、曲に対しての思い入れって、最初に愛情を持っているのは作曲者だと思うので、作曲者が歌詞も書けるなら、それが一番いいのかなっていう。曲によってはもしかしたら、「俺じゃない言葉の発想が欲しいんだよね。これ書いてみてよ」ってことはあるかもしれないですけど。ただ、あまり深く考えてないですね(笑)。
今回はてっきり決めて取り掛かったのかと思いました。
竜太朗:シングルの場合はMVやアートワークだったり、どうしても音楽以外のところもその曲の表現として求められるじゃないですか。その辺も誰が一番やりそうかと言ったら俺かみたいな感じで、じゃあ歌詞も書くかと。そんな考え方も実はあって。やっぱり歌が担うところは大きいから、歌う人が歌詞を書く方が成立するんじゃない?っていうのが、基本なんとなくあるからやります。だけど、例えばシングルの曲を正君が書いたとして、「どうしても書きたいものがあるから、歌詞も書かせてくれ」と言ったら、「どうぞ書いてください」ってなるし(笑)。
バンドを楽しみたかった(ナカヤマアキラ)

今作もやはり皆さんの個性がすごく出ていて、どれが誰の曲か当てやすいなと思って。まず1曲目は正さん作詞作曲の「ライムライト」です。冒頭からプラ好きには「はい、もう好き」という感じじゃないかなと。
正:おー、それはよかったです。
前作の1曲目「あまのじゃく」もオープニングSE的な感じから始まっていったので、音は違えど構成としては今回も同じ形ではありますよね。
正:そうですね。発想自体はもうほぼ一緒です。アルバムの導入として、こういう曲があったらいいんじゃないのかなという自分なりのアイデアを落とし込んだのが、今回これでした。
「ライムライト」は、プラにありそうでなかったワードだなと。むしろなかったっけ?と思って、ディスコグラフィーを確認しました(笑)。
正:この言葉から連想されるようなものは、何かしら表現はしてきたような気がするので、そういうイメージになるのはわかりますね。
チャップリンの映画がモチーフですか?
正:というわけではないんですけど、やっぱり「ライムライト」って言葉を聞いたら、皆まずは連想するだろうと思います。ただ、ライムライトって要は舞台装置じゃないですか。そういうものやチャップリンの映画も含めて、ちょっと演劇性と言うんですかね。プラって、ライブの時にそういうのもすごく大事に表現してきたバンドだと思うので、1曲目にこういう曲を持ってくることで、ライブの時の雰囲気も思い出してもらったり、これから始まるアルバムの世界に、そこで入り込んで来てくれればなという思いで作りましたね。
「プラっと語リー酒」(完全生産限定盤のDVD収録)の予告映像で、アキラさんが「チャップリンだと思わなかった」と発言していましたよね(笑)。
正:なかなかメンバー同士でそういう具体的な話はしないんですよ(笑)。イメージを求められたら話すこともあるんですけど、まずは音ありきなので。
アキラさんとしては、具体的なイメージは知らぬままレコーディングをしたわけですね。
アキラ:ほとんどの曲が基本情報は知らぬままですよね(笑)。
正:歌詞もまだだったからねぇ。
アキラ:これが演劇集団だったら大問題ですよ(笑)。でも、基本軸が音楽なので、知っていれば何かのエッセンスには関わるかもしれないけど、知らないからできませんでしたってことはないわけで、特に大事故は起きないですね。
この曲は歪んだギターも印象的ですよね。
アキラ:定番のロックンロールではない、表現一発の曲なので、そういうのって構築するのがなかなか難しいんですよ。で、手探りで作っていたものが評価を得ると「プラツリらしいですね」とか言われて、それに乗っかっておこうかなというのが僕の本音です(笑)。
(笑)。アキラさん作詞作曲の「no rest for the wicked」は、まず冒頭のユニゾンからカッコいいなと思って。
アキラ:本当ですか。ありがたいですね。やっぱりカッコいいと言ってもらいたいタイプの曲じゃないですか。それが全てかもしれない。実はこれは随分古い曲なんですよ。「こういうのありました。今やってみたいです」と言って。
ライブで盛り上がりそうですよね。
アキラ:そうだね。ライブで盛り上がることが明確に見えたから、今回出したところもあって。書いた当時は「やったー。新曲できた」くらいの感覚だったんだと思います。十何年も忘れていたぐらいだし。
そんなに置いてあったんですね。ちなみに、コーラスの〈痛烈な波状渋滞〉がとても印象に残ります。
アキラ:歌詞は今回書いたものですね。色々取り組み方がありますけど、今面白がって考えられるようになってよかったなと思って。作った当時はそんなの考えられていなかったから。このレコーディングに入るにあたって、バンドを楽しみたかったので「皆でコーラスやろうよ」と。
音源のコーラスは全員ですか?
正:楽器隊3人でやっていますよ。
アキラ:「楽しいじゃん、面白いじゃん」ってね。
次にケンケンさん作詞作曲の「ゆうえん」があります。今回、ケンケンさんの楽曲は2曲ともお洒落だなというのが第一印象で。この曲は要所要所でリズムが特徴的ですね。
ケンケン:確かにそうですね。まだ音を合わせたことがないので、ライブでどうなるのかなみたいな。まだちゃんとアウトロとか把握してないですけど(笑)。アレンジも面白がってくれたらいいなと思って曲自体は作りましたね。今回に合わせてっていうわけではないんですけど、割と新しめの曲です。
以前は他の3人が作らなそうな曲かつライブをイメージして制作していると話していましたが、今回も?
ケンケン:まさに。曲出しをする時に、多分俺が一番遅かったと思うんですよね。数曲出ていた中で、他とあまり被らなそうな曲というか、バリエーションを増やすみたいな意味で多分この2曲を選んだような気がします。
ちなみにこの曲、結構ベースが前に出ているなと思って。
ケンケン:あー、確かにそうかも。
正:なんかちょっとお洒落なベースラインですよね。
サビ前のキメのギターフレーズもお洒落だなと。
アキラ:いやぁ、頑張りましたよ…! ケンさんが欲しているものを欲しているがままに。何も言わないので、多分こういうことかなとすごく頑張って(笑)。
正:イメージを汲み取りながら(笑)。
アキラ:今まで語る場がなかったので、初めて言いましたよ(笑)!
(笑)。各パートのアレンジは、それぞれがアイデアを出して形になっていったんですね。
ケンケン:投げっぱなしが結構多かったですね(苦笑)。最初にザックリ方向性は伝えて、そこからはもう…お任せというか。歌メロに関しても、竜太朗さんに色々なパターンを出してもらいました。