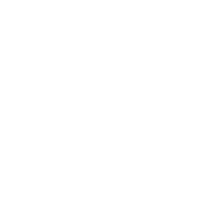ライブを主軸とした『BLOOD STAINS』で描く、生きている実感。血痕=自分たちの存在を残していこう
The THIRTEENが最新音源『BLOOD STAINS』を携え、約3年半ぶりにVifインタビューに登場。シングルながら起承転結を描く全4曲収録の今作は、リリースと同時に開幕する東名阪ツアーに向けて制作されたもので、まさにライブの光景が目に浮かぶ。前回登場時のEP『GLITTER』以降、現在に至るまでの作品の流れを踏まえつつ最新作について話を聞くと、その背景にある真緒(Vo)、美月(G)の思い、そしてThe THIRTEENの今が見えてきた。
今いてくれるファンの人たちを大切にするというのが一番のテーマ(真緒)

The THIRTEENはEP『GLITTER』(2022年1月)リリース時以来、約3年半ぶりの登場です。
真緒、美月:お久しぶりです。
『GLITTER』はヘヴィーサウンドという概念ではなく、新たな音作りでアバンギャルドな大人のロックを魅せるものへ振り切った作品でしたが、その後、『Death Parade』(2022年8月発売)、『A World of Villains』(2023年4月発売)と、より世界観の強いEPが続きましたよね。元々EP『ICY』(2021年3月発売)と『GLITTER』はコロナ禍のライブを想定した曲作りではあったものの、そこからさらに突き詰めたい欲みたいなものが生まれたのでしょうか?
真緒:音もそうなんですけど、世界観、表現の豊かさをもっと作りたいなという感じでしたね。ちょっと語弊のある言い方かもしれないですけど、枠にはまっていることをやり続けると、だんだん劣化版しか生まれなくなったり、模索っぽいものになってしまうという自分自身の愚かさもあって。なので、いろんな部分で突き詰めたものを作って、ライブでそれを表現する技術であったり、自分自身の精神の修行と言いましょうか。そういった意味で、それまで自分たちがやってきたものから、ちょっと枝分かれした広さを作ったという感じですかね。
美月:そういう意味では、あんまり自分の中にないものを広げていく作業でしたね。自分の持っているものの端と端を広げていくような感覚というか。やったことのないことを色々試してみるモードだったので、自分にないものがいっぱいあって、そういう部分では大変でしたけど。でも、勉強していったり突き詰めていくと、やっぱり新しい発見はあったので、良い経験だったんじゃないかなと思っています。
『A World of Villains』で、その方向性をやり切ったことによって、The THIRTEENとしての自由度が増したところもあるのでしょうか?
真緒:なんとなく、いろんなことができるようになったかなと思います。曲のバリエーションが広いと言ったら変ですけど、コントラストが作りやすくなったと言ったらいいんですかね。例えるなら、夜ばかりじゃなくて、朝昼晩がちゃんと作れるようになったというか。ワンマンをした時に、すごく起承転結が作りやすくなったんですよね。いろんな場面、色が増えたというか。イベントで他のバンドさんと一緒にやらせてもらう時も、自分たちに固執した色だけではなく、一つのイベントとして楽しくできる、さらに僕たちもその曲で自信を持って挑めるというような、いろんな意味で広がったところはありますかね。
その後、PhotoBook付きCDという形態でのハードな楽曲『DEVIL INSIDE』(2023年11月発売)を経て、シングル『fragile/閃光』(2024年8月)で『ICY』以前の雰囲気に立ち返ったような印象を受けました。
真緒:そうですね。もうおっしゃる通りというか。今回どんなものを作ろうかというのは、割と一つ前のツアーでライブをしている時に、なんかこういうのが欲しいな、このぐらいのテンポ感のやつ欲しいな、このぐらいの歌モノが欲しいなっていうのが出てきて、毎度そういうものの積み重ねなんですよね。なので、『A World of Villains』でしっかりと自分たちの中で表現というものを色々と勉強して、そのツアーの中で過去の楽曲と『A World of Villains』の楽曲を混ぜ込んで、コントラストを作ってライブを表現していたわけですけど、さらにここからあと1曲増やすなら何を置くかみたいな、常にそういった思考でやっていて。そのたびに楽曲を作っていくというのが、割とThe THIRTEENのスタイルですね。
The THIRTEENはいくつかフェーズがありますよね。もちろん実際にはグラデーションがありますが、大きく区切ると始動からシングル『GAMUSHARA』『WHITE DUST』同時リリースまでで一括り、EP『EVIL MAD SCIENCE』からアルバム『ENIGMA』までで一括り、『ICY』から『A World of Villains』までで一括り、そして現在という。
真緒:あー、確かに。
美月:ホンマっすね。
今年3月に9周年を迎えて、すなわち活動10年目に突入したわけですが、今回の制作にあたって、そのことを意識した部分はありますか?
美月:毎年大事ではありますけど、10年は一つの区切りというのもあるので、そういう意味では、今作というか今年のThe THIRTEENの姿勢として、よりフラットにやっていけたらいいかなと思って。そんな感じで制作に挑んだ気がしますね。
真緒:改めて、このThe THIRTEENという二人でやっているユニットの存在を、追いかけてくれているファンのためにという部分は大きいですね。前向きに二人でやっていけることが色々ある中で、自分たちとしては、楽しくやりつつ今いてくれるファンの人たちを大切にするというのが一番のテーマなんです。ただ、Sadieが復活したことによって、近年The THIRTEENのライブが若干減ってしまったんですよね。その部分ですごくライブをしたい、ライブを主軸にして今回の作品を作りたいというのがあって。9周年を迎えたからというよりは、今決まっている自分たちのライブのスケジュールの中で、とにかくすごくライブ感のある、人間味のあるライブがしたいなというのが一番の考えでしたね。
ツアーに向けて作った楽曲たちが、ちょうどタイミング的に10年目の最初の作品になったと。今回、シングルなのに4曲も入っていて少し驚きました。
真緒:はい、少し欲張りましたね(笑)。
4曲で起承転結がハッキリしている作品だなと感じました。まず、作品のタイトル『BLOOD STAINS』は、どのような経緯で決まったのでしょうか?
真緒:血痕とかの意味合いなので、言葉的にはちょっとおどろおどろしいニュアンスですけど、やっぱりライブって生きてるということじゃないですか。なので、人間らしさとか、誰もが持っているものは血であり、それを血痕として残していこう、このライブツアーの中で自分たちの存在を残していこうっていうような意味を込めて、『BLOOD STAINS』というタイトルにしました。
自分が想像していたもう1個上の段階のものになっている(美月)
リード曲の「CALLING」は、印象的なイントロのギターリフがThe THIRTEEN節だなと思いました。
美月:はい(笑)。やっぱりライブが減っていた分、ライブをしたくなるような作品にしたいなというのはあったので、意外と捻らずに、キャッチーな要素をすごく意識して作っていました。だから、ライブが想定できるようなもので、あまり考えて作らなかった気がします。いつもはもうちょっと捻ったほうがいいかな、どうしようかなみたいなことを考えたりするんですけど、今回は意外と素直に流れでいったものをそのままパッケージしたので、そういう意味では、らしさが出ているのかなと思いますね。
アウトロは、なかなかこだわりがあったようで。
美月:最初、イントロのフレーズを貼り付けて終わるみたいな、よくある手法にしようかなと思ったんですけど、アウトロで物語が終わるようなニュアンス、エンドロールっぽいアウトロにしたいなというイメージがあって。なので、あえてサビ終わりでハモリのギターのそんなに長くないフレーズを入れています。
この曲の英語と日本語のバランス、シームレスな響きというか、違和感のない流れは、真緒さんの技が光っているなと。
真緒:やっぱり英語と日本語を混ぜると、意味も知らないまま流れていってしまうこともありますし、混ざりと言葉の呂律と難しい部分があるんですけどね。でも、自分の中で客観的に聴いた時に、日本語の言葉としてのメッセージはしっかり残っているので、そういう意味ではこの曲の持っているイメージは伝わるんじゃないかと思っています。
サビでは「Oi Oi」コーラスが入っていて、ラスサビでは長いシャウトがずっと鳴っていますが、これらは美月さんの担当ですよね?
美月:そうですね。サビの「Oi Oi」は、ライブで皆さんと一緒に言えたらなと思っています。大サビはどうなるかわかんないっす(笑)。今までの曲も、コーラスっぽい皆でワイワイする系のやつはそのまま活かしているんですけど、サビ裏でシャウトしているやつは、結構ライブでは端折っていることが多いので、多分そっちの方向になるんちゃうかなとは思っています。
ちなみに、2サビ後にシャウトからオクターブ下の落としブロックが入って、そこからのラスサビへの展開がさすがだなと。
真緒、美月:あ〜。
美月:目まぐるしい感じですよね。
真緒:自然となんかそうなっていったという、多分僕たちの展開の癖なんでしょうね(笑)。ガッと激しくいって、そこからピタッと静寂さを作って、そこから駆け上がるような構築で、ドラマチックさを作るというか。それも多分、僕と美月君のあうんの呼吸みたいなものがあるんじゃないかと思います。
では、「CALLING」に関して、お互いの「さすがだな」と思うポイントを教えてください。
真緒:僕、曲を作る時、結構地味で、「うっひょー! できたな!」みたいなことはないわけですよ(笑)。要はデモの段階とレコーディングをする直前の形は結構違っていて、例えば歌を先行で作るものって、ある程度このコードで乗せといてと言って、自分が歌を乗っけてからギターをはめることが多かったんです。最初のデモの段階では、構築と大きなギターフレーズ、わかりやすくピックアップできそうな部分だけはあるんですけど、他の細かなアレンジは後になってくるので、これ最終的にどうなるんやろうっていう感じではあるんですよね。でも、最終的に必ず満足する、素敵なバックが仕上がっているな、編曲できてるなと思うので、毎度のことながらその辺は言わずもがなの安心感がありますね。
美月:曲の作り方的に、うちは特殊とよく言われるんですよね。多分、他のバンドさんは、デモを持ち寄ったものにメロディを乗っける感じだと思うんですけど、うちは大体作る段階で一緒にいるので、じゃあ今からイントロ作りましょう、Aメロはこんな感じかな…ああだこうだ…みたいな感じで。作っている段階で多分ここはシャウトでいくわとか、メロディも何も乗ってないオケだけで進んでいくので、それがある程度完成して清書したものを聴くと、こういうイメージで来るかなと自分が想像していたもう1個上の段階のものになっているんですよね。そういう意味では、1個きっかけを作ってくれたり、フックになるようなものを提示してくれるなと。「CALLING」はサビのバックのコーラスとメロディの抜けのバランスとか、元々のやつから1回変わっていて。元々はもうちょっと単純な感じだったんですけど、メロディが映えるようなものに変わりつつ、バックコーラスも入ったので、さすがやなと思いました。
先日MVが公開されたばかりですが、こういうシンプルな演奏シーンメインというのはThe THIRTEENには珍しいなと。
美月:そうっすね。それこそ『A World of Villains』の表題曲「QUEEN」のMVは、大世界観でしたし。今回は楽曲のニュアンスもあったので、逆に演奏メインでいこうと。それと、よくあるザ・バンドの、メンバーが円形の立ち位置での演奏シーンというのを意外とThe THIRTEENではやったことなかったので、単純に楽しかったですね。バンドしてるなって感じしました。
真緒:MVも今までたくさん撮ってきて、雰囲気ものとか、ほぼメンバーが演奏せずに内容だけ進む映画のようなものとか、いろんなパターンがある中で、結局こういうのが一番いいなとは思いましたね。わかりやすく演奏しているものがバンッと届けられるというのが。まぁ逆に、いずれまたもっと世界観を重視したものがいいなとも思うんでしょうけど(笑)。ただ、今のタイミングで言うと、メンバーの顔が見えて、ライブ感があって、動きがあるようなものがいいなと思いましたね。