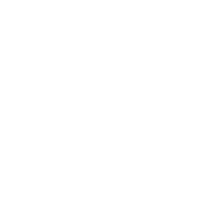『夜、カルメンの詩集』が映し出す清春の美学。
積み重ねてきた愛おしい日々と、理想の清春像。そこにある真実とは――。
昨年、全66公演に及ぶプラグレス形式でのステージを完遂させると同時に、その世界観をスタジオレコーディングで再構築した『エレジー』をリリースした清春。そこから僅か2ヵ月余というタイミングで、オリジナルアルバムとしては通算9枚目となる『夜、カルメンの詩集』が完成を迎えた。50歳という節目を目前に、これまでの清春の活動と思いが全面に反映された今作は、果てしなく美しく深い愛情が詰まっていると共に、彼の美学が映し出されている。そんな最新作についての話を軸に清春の口から語られた、音楽をやる意味、理想の清春像とは。そこには、積み重ねてきた日々への誇りと先を見据える49歳現在の清春の真実があった。
◆ちゃんと美しく強く、確かなものを作っていけるような年齢
――前回のインタビュー時、清春さんとしてはリズムレスアルバム『light~saw the light & shade~』と『shade~saw the light & shade~』(2008年発売)を1作品として捉えて、『SOLOIST』が9枚目のアルバムという認識で、「自分がやっている音楽はこういうものなんですというものが、10枚目で総括できると思っている」と言っていました。実際、オリジナルアルバムとしては今作『夜、カルメンの詩集』が9枚目になるわけですが、10枚目という意識が強いですか?
清春:今回はそれどころじゃなかった。レコーディングが問題に次ぐ問題で。途中、ぶん投げて止めようと思ったことが3回くらいありました。途中からディレクターを来させなかったし、だったら最初からいなくてよかったじゃんと。最後のほうは終わらせるということにフォーカスしてしまった。それでも発売日は延期になりましたし。だから、録っている時はすごく良いなという愛情はあったんだけど、完成したという達成感がないですね。僕と三代堅さん(アレンジャー)の中では「んー…」という感情のまま終わっていて、僕らが若かったら全部ぶっ壊していますねという。
――12月にリリースされたリズムレスアルバム『エレジー』はスムーズだったんですか?
清春:『エレジー』は三代さんと(中村)佳嗣くん(G)、大橋(英之)くん(G)、当時のエンジニア、この4人で出来ちゃったので、あとは歌うだけで。その時期はプラグレスライブも散々やっていたし、使う楽器も少ないし、そんなに問題はなかったんですよ。『エレジー』の後半くらいからちょっと匂うぞと思っていたんだけど、今作のオケ録りが終わった頃から問題が出始めたんですよね。本当に僕が今50歳くらいで良かったなと思います。
――紆余曲折ありながら、完成に辿り着いたということで。
清春:未完成の中の完成だね。本当は12曲録っていたんですけど、10曲収録になりましたし。もちろん、入っている曲のアプローチ、バランス感とかはとても良いと思いますよ。
――以前、音数が少ないものにしたいと言っていましたよね。
清春:今回は結構ゴージャスになっちゃったなと思っていて。前半はエレキギターがほとんど入っていないだけであって、パーカッションや鍵盤は割と入っちゃっているので、その辺は三代さんとの意思疎通が足りなかったかなと。2月9日にやった25回目のデビュー記念日ライブで、ちょっと問題が出たんですよね。レコーディングで入っている音だから出したほうがいいということで、CD ver.の同機を流したんですけど、ライブで誰もプレイしていない音がバンバン聴こえてきて、バンドとカラオケが一緒に演奏しているようなものに近くなっちゃうのが良くないなと。なので、次回はもっと音数を減らしましょうと話しています。隙間を隙間っぽく聴こえさせないような補強が入っているんだけど、今の僕だともうちょっと間がもつと思うんですよね。…でもこれは9枚目だったんですね(笑)。
――結果的に良かったかもしれないですね。昨年、プラグレスライブ「エレジー」66公演があり、これまでバースデーライブはバンド形態が常でしたが、49歳の誕生日は初めてプラグレスライブで迎えて、さらに66公演の完遂と同時にアルバム『エレジー』がリリースされたことは美しい流れでした。
清春:「エレジー」の他にもライブはあったし、トータルすごい本数をやって、あれが限界だったなと思いました。消耗度というか。長くやったり、たくさんやることを選ぶ年齢ではないのかなという答え。誕生日や『エレジー』が出せたことはすごく良かったんですけど、歌い過ぎていて声が変わっていく自分を感じていました。それが渋いというところで収まっていれば良いんですけど、あまりにも声が出ていない状況のままレコーディングをしなければいけなかったり。そういう中でも歌えるような術は身に付いていったんですけど、せめてレコーディングはもう少しクリアな状態でやれたら良かったなというのがあって、年齢と今の活動のバランスなのかと思いましたね。年末年始にレコーディングをして、リリースして、もうツアーが始まるじゃないですか。休んでないなと。
――ずっと動き続けているイメージはありますね。
清春:あとはバーとアパレルのこともあるので、本当に休んでない。割と日曜日にアパレルやグッズのデザインをしているし、本当に…気絶して眠る毎日です(笑)。
――(笑)。今作はとても美しくて、愛の詰まった作品だなと感じました。これまでも、ディープなファンの方々にしかわからないことが楽曲の随所に散りばめられていましたが、今作はそれがより強まっているなと。
清春:そういう感じがするよね。ちゃんとライブに来てくれて、僕のことを大好きだと思ってくれて、生活の中に必ず僕の曲や活動があるという人にしか響かないような部分は今回も多い。フラメンコやスパニッシュ的な雰囲気というコンセプトの部分は外にもちょっと向いているけど、それ以外は僕のここ10年くらいを追っていないと、何を歌っている歌詞の内容なのかわからないとは思います。
――逆に言えば、わかる方々は涙が溢れる作品だと思います。
清春:僕らの年代になると、そういうものもありですよね。
――清春さんの活動が全て繋がっていることがわかる作品でもあります。そもそも今作のタイトルは2016年と2017年のツアータイトルと同一ですよね。
清春:ツアーをやっていた時からすごく良いなと思っていたので、どこかのMCでも次のアルバムのタイトルはこれだからと言っていましたね。とても邦楽的であり、陽気な感じもしなくて、でもダークサイド過ぎず、美しくもありロマンチックでもあり情熱的でもあるというタイトルかな。「夜」というのが良いですねぇ。
――1曲目が「悲歌」、すなわち“エレジー”で始まるのも美しいです。
清春:最初はこれを1曲目にしようとは思っていなかったんですけどね。むしろ最後のほうかなと。歌入れをしてミックスの時にすごく良かったので、これは1曲目だなと思いました。
――「赤の永遠」は少し前まで「雨の憧景」という仮タイトルだったと思いますが、なぜ「赤の永遠」になったのでしょうか?
清春:どちらも歌詞にある言葉ですけど、カルメンのイメージに合わせたんでしょうね。「赤」は『夜、カルメンの詩集』を表していて、スパニッシュやフラメンコはどういう音楽か検索すると「情熱と哀愁」と出てくるんですけど、それが永遠というタイトルのほうが良いなと。「永遠(とわ)」という言葉がとても気に入っているんです。今ここにあるものが永遠に続くという意味と、ずっと遠くにあって掴めないという、ダブルミーニング。僕らとファンの人たちの関係は永遠なんだよっていう安心感もあれば、目指すところはどこまでも遠い…安心する言葉でもあれば、途方に暮れるような言葉でもあるということですね。
――「三日月」には〈上がった階段 それは永遠と違う〉という歌詞がありますよね。
清春:最初は自己表現、人とは違う何かをやりたいということで音楽を選んで、その音楽を続けるために売れなきゃいけないという時期がある。もしくは、Zeppをやったら武道館とか、そういう階段を駆け上がるという時期を誰もが経験して、音楽がそのための道具、材料になっちゃう時があるんですよね。でも、もう自分の作品はそういうものじゃないんだよと、〈永遠と違う〉と言って、逆説的に永遠であるということを言おうと。
――なるほど。
清春:どの曲でも今がそれなんだよって言いたいわけです。例えば女の子って、結婚、出産、家族でこういうところに行きたい、そうすれば周りと同じような幸せが私にも訪れる…それをクリアしておきたいというのがあって、男の人はそれを叶えるべく頑張るんですけど、最終的にはそういうことではないじゃないですか。付き合い始めて1年でも1週間でも、この相手と共有したいのはこの形なんですっていうのを提示して、これ以上はなくて、これをずっと続けられるか、続けられないかということなのかなと思うんですよね。それは僕とファンで例えても同じで。僕が作っている作品やライブにおける楽しさというのが、今、それぞれの子たちの生活に必要だから来てくれているんでしょうけど、それ以上の答えなんてないんですよ。作品の美的レベルや、聴いていたら安心する、単純に声が好きとかでいいんじゃないかなと思っていて、それを言っているだけじゃなくて作品で具体化したいんですよね。僕らって、とても儚いことをやることで、お金をもらっているのかなと思っていて、それを確かな儚さにしたいんです。
――確かな儚さ…。
清春:ファンの人にとってね。僕らの仕事って、頑張っているとかじゃダメなんですよ。音楽を仕事にして、上がっていって、それが過ぎていく瞬間ってあって。そこでやっと俺はなんで悩んでいるんだろうって気付くようになるんだと思うんですよ。上っている時は気付かないし、あまり気にならないんだけど、何年かして、それがなんだったんだろうということを、今ようやくCDに詰め込めるようになって落ち着いてきた。それによって確かな作品になってほしいという段階なのかなと思います。
――確かに、清春さんが普段から言っていることが、今作の歌詞に具体的に入っているなというのは、とても感じました。
清春:僕のことを好きでいてくれて頑張っている後輩の子たちは、本当に応援しているし、自分の子供の成功を喜ぶかのような時もあるんですよ。でも、僕らの世代が何をやるのかというと、もうそのスタンスじゃダメだというのを感じてる。僕らは作品をちゃんと美しく強く、確かなものを作っていけるような年齢なのかなっていう。そうじゃないと、ファンの人も疑問になってくると思うんですよね。何が残るかというと、良い作品をファンも僕も同じようなレベルで共有できるかということでしかなくて、自分の作品を客観的に「素晴らしいな」と言えるようでありたいんですよ。そこにはまだ届いていないんですけど、ファンの人は好きな曲が何曲もあると思ってくれたら、その積み重ねで「清春さんはいつも心の琴線に触れる曲を書いている」となる。そういうことでしかないんですよ。
◆こうであってほしいという“清春”が常にいる

――今作収録曲の7割が既にライブで披露してきた楽曲ですよね。
清春:ライブでやってないのは「悲歌」「TWILIGHT」「三日月」だけですね。
――10曲全てに〈愛〉というワードが含まれていて。
清春:え、それは知らなかったです(笑)。すごいなぁ。なんてロマンチックな。
――〈夜〉〈会う〉も多いですね。
清春:そうですね。〈夢〉が減ったと思います。
――それは意識的に?
清春:あえて省きましたね。〈夢〉という言葉が自分の中でキャッチーじゃなくなったんですよね。歌った響きもそうだし、少し愛着がなくなったというか。〈愛〉や〈会う〉を歌っているほうが今は良いんです。あと、〈君〉が減って〈あなた〉になりましたかね。〈愛〉が増えて〈夢〉が陰を潜める、年齢のせいでしょうか(笑)。
――名言です(笑)。でも『SOLOIST』の時点で、ラブソングが多かったですよね。
清春:もう、そんなに歌いたいことないんですよ。10年くらい前にもそういう問題はあったんですけど、多分ツアーとかをしていなかったら、歌いたいことは本当にないんです。あとは聴いた人や、自分が俯瞰して“清春”を見た時に、今、この年齢になってこういう男であってほしい、こういうものを歌っていてほしいという理想が歌詞には詰まっている気がしますかね。これは初めて言いました(笑)。
――そうなんですね(笑)。
清春:50歳って、10代~40代の人たちを包括できるというか、男性で「清春、今もすげーな、カッコいいな」と投影して聴いている人もいるじゃないですか。そういうもののもっと高いレベルの目線で歌ったことが、若い人や同世代の人たちに刺さってもいいし、まだまだ頑張ろうと思ってもらってもいい。けど、自分が思っている、こうであってほしいという“清春”が常にいるんですよね。40歳の時とはまた違うカッコいい男になってほしい。作詞している自分が、歌っている清春さんはこうであってくれたらいいなと、同調させるというか歌わせるというか。映像や写真では周りの皆が僕をちょっと若く仕立ててくれるけど、歌詞を書いている自分って、リアルタイムであってほしいなと思うようになったんですよね。前は、嫌なことは忘れて、この素敵な時間を止める存在であってほしい、ロマンチストでいてほしいみたいな感覚はあったんですけど、今は潔くあってほしい、動じない男であってほしいとなってきました。ある種、諦めることや捨てること、それをいつまでも嫌だと言わない自分でいてほしいなとか(笑)。
――森清治さん(本名)から見た、アーティスト清春さんの理想像。
清春:そうです。多分、まだ出来ていないからだと思うんですよ。その歌の解釈が数年後にクリア出来ていれば、素敵な人生の過ごし方をしている人になれるんだろうなと。
――少し先の未来に、こうであってほしいという感覚ですか。
清春:多分ね。ファンの人が思っている清春さんは、自分からは微妙にわからないんですけど、ただ、普段のほうがちょっと落ち着いているのは明らかなんですよ。言いたいことを言っている清春さんって、どこか演じている部分もある。でも、森さんはそんなことを言っても何も変わらないことはとっくにわかっているんですよ。ただ、清春像というのはあって、言いたいことを言ってほしい、清春さんならこうだろうっていう。だけど、作品の中の自分というのは、やっぱり未来なんですよ。
――いつも、どのくらい未来を見ているんですか?
清春:5年先だね。もう55歳の時を想像していますよ。45歳の時には今を想像していたけど、結果は思ったよりも大人になってないんだよね。思ったより完成されてないし、俺、堕落しているなと思うから、残っている先輩方をより見るようになるんです。僕だったら親父以外で背中を追う人となると、MORRIEさんしか浮かばないけど、彼との会話の中でも僕と全然違うなと思う時もあるし、テレビやネットを見ていて55歳、60歳で表現という仕事をされている方が話していることはすごく気になります。若い子の意見よりも上の人の意見が気になるように、よりなったんだよね。
――常に先輩を見ているというのが、清春さんらしいです。若い世代から刺激を受けるというタイプの方もいますよね。
清春:自分が若くいられる方法って、そのどちらかだと思うんですよね。若い子とたくさん交流して刺激を受けて、自分も若い世代のことを勉強していくというタイプも多いし。だけど僕はそうじゃない。もちろん、僕に憧れてくれている子たちの存在は知っていて、応援してるし、生き残ってほしいと思うんですけど、自分が現役でいるうちはね…。
――追う対象がいるほうが、成長できる気はします。
清春:そうですね。若い子たちから「今日のライブ、カッコよかったです」とか言われるのは、もちろん嬉しいけど、あんまり身にならないというかさ。MORRIEさんから「あそこは良かったね、あそこはイマイチだった」と言われたほうが、嬉しいし解りやすいんです。だから、そういう目指す人がいなくなった時、どう歌っていくのか疑問だし、自分との戦いなんてすぐに終わっちゃうんだと思うんですよ。
――一番難しいことですね。
清春:過去の自分との戦いを繰り広げている人は、たくさんいると思うんだよね。黒夢で言ったら、最終的には「少年」とか「MARIA」で地名度が確立したから良かったんですけど、デビュー当時のちょっとキラキラしていた時期を打ち消したいと思っている時期はあって。だけどそういう戦いって、無意味だなというのはもうわかっていて。でも、それをずっとやらなきゃいけない人たちっているんですよね。一体何と戦っているのかな、と思えちゃって。やっぱり追いかける対象がいないんだと思うんですよね。僕なんて幸せで、MORRIEさんのことを好きだと言えている自分が好きですし、僕が音楽を神聖な気持ちでやれているのって、あの人に少しでも追いつきたいという、そこだけなんです。だから、ライブも必ず観たいし、その場のムードも感じていたい。単純に音楽や声が好きという部分もあるんですけど、自分が続けていく上で彼の存在は必要不可欠なんです。
――追いかける対象がいるというのは、幸せなことですね。
清春:他界して伝説のミュージシャンになっている人はたくさんいるけど、生きている人には敵わなくて、生きて活動を続けて、自分を探して完成させていこうとしている、そういう人がまだいらっしゃるのは素晴らしい。MORRIEさんがいなかったら、僕のここ何年かのアルバムも生まれてなかったと思うんですよね。あっても、さほどチャレンジしようという気持ちはなかったと思う。MORRIEさんのソロアルバムの音像は理想的で、僕は1st、2ndアルバムの時に結構意識していました。それよりもソロで今もチャレンジしていらっしゃるという崇高さです。僕の後輩の子たちはまだ上った階段を降りていないので、この意味が現状はわからないんですよ。MORRIEさんの後輩だと、僕を筆頭に音楽をやる本当の意味がわかってきている。それはファンの人たちにも言えることで。自分の10歳くらい下が一番のリアルタイム世代なので、僕が『少年』を出した頃に15~18歳という一番多感な時期だった子たちが、今、37~40歳になって、家庭を持って過ごしていても、まだライブに来てくれて、その人たちがこれからもっと「清春がやっていることは、わかる」というふうになってくると思うんですよね。