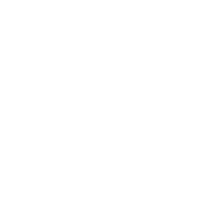20周年の後半戦の幕開けを飾る待望のリテイクアルバム第二弾が遂にリリース! 輝きを増した不朽の名曲たちが世に放たれる
20周年という記念すべき年を駆け抜けているlynch.。今回完成したのは、ライブでも必ず耳にする名曲たちが収められた『THE AVOIDED SUN』(2007年4月リリース)と『SHADOWS』(2009年7月リリース)の名盤2作品に、書き下ろしの新曲「BRINGER」を含む全27曲が収録された4枚組の豪華なリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』だ。完成度の高さはもちろん、現在のlynch.の勢いをそのまま閉じ込めたような今回の作品について、20年前のlynch.以来、共に歩んできた葉月(Vo)と玲央(G)の二人に話を聞いた。
前作で生まれた“欲”がこのセカンドリテイクアルバムに反映されている(玲央)

意外にも、葉月さんと玲央さんのお二人での取材はVif初ということで。
葉月:あれ、そうでしたっけ?
玲央:そういえばそうかも。10周年のときは晁直と三人でしたよね。
なかなかのレア回です。さて、精力的に活動を展開してきた20周年もいよいよ終盤戦という感じでしょうか。
玲央:むしろこれからですね。9~12月に主催イベント「BLACK BEAUTY BEASTS」、LIMITED 3 DAYS、リリースツアー、東京ガーデンシアター公演等々が詰まっているので、ここからが後半戦という感じです。
そんな多忙な後半戦の幕開けにリテイクアルバム第二弾がリリースされるわけですが、今回リテイクした2枚のアルバムにはどんな思い出がありますか?
玲央:前作でリテイクした最初の2作品は、バンドをスタートさせたばかりだったこともあって、とにかく我武者羅だったなという印象です。lynch.とは何か、というものがまだ固まっていなかったというか、自分たちの共通の認識として持ち合わせていなかったなと。でもそれ故の無鉄砲さや勢いは、その頃にしか出せないものでしたね。振り返ってみると、今回の2作品からは、lynch.らしさとは何かというところを明確にして、それをリスナーに届けたい、という意思が強く感じられるなと思います。
徐々にバンドの色が見えてきた頃に作られた2作品ですが、いずれもかなり完成度が高いですよね。
玲央:ありがとうございます。そう言っていただけることがすごく多くて、ありがたい限りなんですよ。
前回のインタビューで、特に結成後初の音源であるアルバム『greedy dead souls』について、「最初の作品だけに一番距離を感じる」と話していましたが、今回の2作品はいかがですか?
葉月:この作品を作った頃はまだ、できあがった後に「何でもっとこうできなかったんだろう」と思っていた時期ではあるんですよ。僕はlynch.が始まってから10年くらいそんな感じでしたね。アルバム『GALLOWS』(2014年4月リリース)で初めて、自分の思った以上のものになったという喜びがあったんです。それまでは、「何でできないんだ」ってずっと思い続けていましたから。でも、そう思うからこそ伸びていくんだと思うんです。
今回リテイクするにあたって、ここを直したいという箇所はありましたか?
葉月:いくつかありましたけど、基本的には少なかったです。当時できなかったことを、今回やったという感じですね。前作のリテイクアルバムでは、シャウトもオリジナルの発声を研究してやったんですけど、今回はそんなに意識しませんでしたし。原曲を聴いての驚きがなかったので、割と今らしくやりました。変えたいなと思ったのは、「I DON’T KNOW WHERE I AM」の歌と、「CULTIC MY EXECUTION」の間奏ぐらいかな。
「CULTIC MY EXECUTION」の語りの〈メメントモリ〉の後のグロウルが、今回どんなふうに変わっているのか注目していました。
葉月:一番低いやつですよね。あれは、ガテラルになるのかな。原曲はグロウルだと思うんですけど、今回はガテラルのところまで下がったと思います。あの部分は、やり方が全く違うんですよ。当時はガテラルまではできなかったんですけど、今回はこういう形で収録できました。当時できなかったけど、今はできることって本当にたくさんあるんですよ。
葉月さんの歌の圧倒的な成長を感じます。「CULTIC MY EXECUTION」の語り口調の変化もインパクトがありますね。オリジナルの音源では低い声だったものが、明瞭になって。
葉月:演説みたいな感じになりましたよね。あれはライブを経てどんどん変わっていったんですよ。音源通りだとライブでは聴こえないので。
今回の2作品の楽曲にはライブの定番曲が揃っていますし、ライブの中で完成度を高めていった楽曲が多い印象です。
葉月:そうですね。それもあってレコーディングの時に、この曲をやるならこうだよね、というのがパッとできたんです。なので、この曲も確かワンテイクだったはず。ライブで育っている曲はサラッと終わりましたね。
逆に、一番テイク数が多かったのはどの曲でしょう?
葉月:やり直しが多かったのは、やっぱり「I DON’T KNOW WHERE I AM」じゃないかな。歌詞を書いたばっかりで慣れていなくて(笑)。歌い回しがなかなかはまらなくて、ああでもないこうでもないってやっていましたね。
玲央さんは、当時との違いを最も感じるのはどの部分ですか?
玲央:まず当時と環境が違うというのが一つ、あとはギターのリアンプ作業を僕とエンジニアのЯyo君の二人でやっていたんですけど、アンサンブルを考えた時にリズム隊と悠介のギターのノリが気になるところは、ちゃんとその穴を埋めるように僕の方で全部弾き直したんです。当時は、予算や時間の関係で録り直せなかったところを、自分でその場で対処できるような環境と時間をいただいていることが大きな違いですね。時間がないと言いつつ、「やるならやっちゃおうよ!」という感じで、その場ですぐに対応できたのは当時と明らかに違うなと思います。リテイクしたことで音が洗練されていて、一聴すると上品に聴こえるかもしれないですけど、そういう部分も含めて今回の方がむしろバンド感は出ている気がします。
その場で録り直していったというのはすごいですね。
玲央:音はデータ上でも直せるんですけど、その場で弾いてしまった方が絶対に仕上がりが良いので、バンバン弾きました。多分、直さなくてもリスナーは普通に聴けるんですよ。ミュージシャンとして、プレイヤーとして、バンドとして気になるところは、おそらくリスナーとは違うんです。ただ、お互い満足しないと作品を出す意味がないじゃないですか。直さずに出しても不正解ではないので、聴いている方は「ああ、これがlynch.の最新音源なんだ」となると思うんです。ただ、もっといけるでしょうという話で。
プレイヤーとしてのこだわりを感じます。玲央さんのギターパートでの大きな変化はありますか?
玲央:大幅には変えていないです。ただ今回、「I DON’T KNOW WHERE I AM」をアコギで弾いたんですよ。メンバーの共通認識として、録り直しをするときにオリジナルのイメージを尊重したい、という思いがあったんですけど、「I DON’T KNOW WHERE I AM」は最初のお披露目がイベントライブだったんです。音源化されるよりも先にイベントライブでお披露目していて、その時にアコギで弾いているんですよ。それで今回、この曲のギターをどうするか葉月に相談したら「アコギじゃないですか」という意見が出たので、やっぱりそうだよねということで、アコギで弾きました。
オリジナルのさらにオリジナルなんですね。
玲央:そうです。でもЯyo君から「玲央さん、これアコギが入っていますけど、エレキは入らないんですか…?」って確認が来まして(笑)。どうも『SHADOWS』というアルバムのイメージが強すぎたみたいなんですよね。「なぜかここにアコギが入っています」という言い方をされたので「アコギで弾くんです」と伝えたんですけど(笑)。
『SHADOWS』自体が強烈なインパクトのあるアルバムですものね。Яyoさんの気持ちがよくわかります(笑)。
玲央:でも、実際に抑えるポジションやキーを考えたら、アコギの方が適切だったりするんですよ。なので、今回録り直すにあたって、オリジナルのオリジナルでやった方が面白いかなと思ったんです。
ツアーでもアコギの「I DON’T KNOW WHERE I AM」が聴けるんでしょうか。
玲央:そのつもりです。既にスタンバイしているので、楽しみにしていただきたいです。
玲央さんは10周年のベストの時に、「メジャーデビューしてギターテックさんとお仕事をしたことで考え方が変わって、ギターを全部録り直した」というお話がありましたが、今回の作品では?
玲央:あの時に録り直しをして、今回さらに録り直しました。ただ、10周年のタイミングと今で環境が変わっていて、音に対する捉え方や楽曲に対するアプローチの幅も広がっているので、あの頃よりも良いものが作れている自信はありますね。
今回のリテイクで音がかなりクリアになって、細部までよく聴こえるので楽曲の魅力が再確認できました。
玲央:ありがとうございます。それは、第一弾のリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』があったからこそなんですよ。あの作品を作った後で「もうちょっとこうできたよね」という、“反省”よりも“欲”がこのセカンドリテイクアルバムに反映されているんです。前作がなければ、このリテイクアルバムは今の仕上がりにはなっていない。そういうものは全部積み重ねなんですよ。いつも言っていますけど、アルバムを作るというのはその時その時の記憶なわけで、記憶であり記録なんです。それを更新していくのがレコーディングでありアルバムだと思うので、そう言っていただけるとすごく嬉しいですね。
前作で生まれた“欲”が、すぐ次の作品に生かされるというのは素晴らしいスピード感ですね。
玲央:ここ1年ぐらいで、めちゃくちゃ曲を録ってますからね。葉月は他のプロジェクトも含めると、1年でかなりの数の歌録りをしているんじゃない?
葉月:60曲ぐらいですね。
玲央:尋常じゃないですよね。僕も多分60曲は超えていると思うんですけど、1年というスパンで考えると、ここまで録ったのは初めてです。でも、意外とやれるものだなと思いました。こなしているという意味じゃなく、ちゃんと頭の中でパーテーションで区切ってやれているなという感じなんですよ。とは言え、僕はエレキ楽器だからプラグを繋げば音が鳴りますけど、葉月は声という生楽器じゃないですか。体調管理から声の調子まで色々大変だろうに、よくあのツアーの合間を縫ってこの歌が録れるなと感心していました。
レコーディングは前作のツアーの合間だったんですね。
葉月:そうなんですよ。ツアーの合間とか、終わった直後とか。でも、もうこういう風にはやらないです! もう絶対やりたくない(笑)!
このハードスケジュールは、葉月さんの声の出し方が昔に比べて飛躍的に向上したことで実現できたのでしょうか?
葉月:どうだろう。昔よりも良いところもあれば勝てないところもありましたから。もちろん、変わったことで良かったことの方が多いですけどね。
玲央:逆に、ツアー中だったから良かったのかもしれないとも思うんですよ。ライブで実際に聴いている人たちが目の前にいる情景をインプットしたまま自宅に帰って、すぐにギターを手に取る毎日だったので。もっとこうした方が熱量が上がるよな、というアイデアをすぐにアウトプットできる状態だったんです。…でも、もうやらないですけどね(笑)。
相当辛かったんですね(笑)。
玲央:もうちょっと落ち着いてやりたいです…。1年で60~70曲はきついので、自分からは企画しないですね(笑)。
晁直さんは10周年の時に「liberation chord」と「from the end」を録り直したそうですが、今回はそこから改めて変えたんでしょうか。
玲央:ドラムはそんなには変えてないはずです。10周年の時は、弦楽器は録り直す、ドラムに関しては今のミックスのままでやろうという話だったんですけど、僕がインディーズの時にお世話になっていたレコーディングスタジオにデータをもらいに行ったら、その2曲だけドラムのデータが破損していて、どうしても復現できなくて。実は今回の作品で、ハウリングの音とかフィードバックの音とか、当時の音を真似しようと思ったんですけど、出なかったんですよ。具体的に言うと「PROMINENCE」の間奏のリフの合いの手の隙間なんですけど、ハードディスクから抽出しようにも破損していて、「Pro Tools」というDAWソフトのフォーマットでは再生できなかったんです。それで意地になって、ファイル名が番号しか書いてない300ぐらいある音声データを、一つずつ聴いていったんですよ。聴きながら「これは…違う」「次…違う」「次…あ、これ間奏の2回目」とか言いながら。
すごい執念ですね。そして、ちょっと怖い…(笑)。
玲央:まさに執念でした(笑)。その素材をЯyo君に投げて、今の音に合体させてくれってお願いしたんですけど、そのときに同じこと言われました。「玲央さん、怖い」って(笑)。でも、あの音は偶然の産物なので、あの時にしか出せていないんです。今は環境がいいから、ああいうヒステリックな劣化した音は出なくて。だから今回はそれをミックスさせました。ついでにキメのギターリフも、当時のやつを20%ぐらい混ぜておいてって頼んだんです。そうすると、ちょっといなたい(野暮ったい)感じが出るんですよ。今回はそんなハイブリッドな仕上がりになっています。
かなり手が込んでいることがわかりましたが、やっぱり怖いです(笑)。
玲央:あはは。データを一つずつ聴いていくんですけど、「次はファイル名『0018』…」とか言いながら検証して、波形を見ていました。「あ、やっぱり間奏の2回目で合ってる」って言いつつ(笑)。
前回は、ノイズが嫌だからとアース線を引っ張ってご自宅の庭に鉄柱を刺していましたし、玲央さんの新たな怖すぎる伝説にワクワクが止まりません。
玲央:Vifさんはこういう話を喜ぶだろうなと思ったんですよ(笑)。