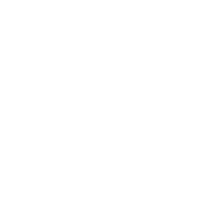バンドの黎明期を支えた全21曲に新たな息吹を宿し新曲も加えたリテイクアルバムが完成! 20周年の“特別記念盤”の魅力に迫る
20周年という大きな節目の年を迎えたlynch.。彼らが周年プロジェクトの第4弾に据えたのは、インディーズ時代の2枚のアルバムと、会場限定盤やボーナストラックなど現在では入手困難な楽曲たちをリテイクし、さらに新曲も加えた一大作品『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』のリリースだ。「今回は、あの時こうしたかったんだろうなということをやろうと思った」とは葉月(Vo)の談だが、20年に渡ってキャリアを積み上げてきたlynch.らしい、圧倒的な完成度を誇る作品になっている。20周年を彩る今作について、葉月、玲央(G)、晁直(Dr)に話を聞いた。
20周年の記念品のような作品

20周年おめでとうございます。周年プロジェクトが始まって間もない頃の、晁直さんの「1月からこんなに忙しいの過去にない! これが20周年か!」という言葉が気になっていました。
晁直:今も忙しいですよ。例年1月から3月って暇な印象だったんですけどね。
葉月:1月に何をしていたか記憶がないんですけど、晁直さんは1月、僕は2月がヤバかったですね。
周年プロジェクトの内容も次々発表されていますが、このタイミングで20年前の音源である『greedy dead souls』と『underneath the skin』をリリースすることにしたのはなぜだったんでしょう?
玲央:以前から、再販してほしいという声を多くいただいていたんです。でも、当時とはメンバー構成も違いますし、出すのであれば特別なタイミングでやりたいと思っていて。それで今回、20周年というタイミングで、現体制の5人で録り直したリテイクアルバムをリリースしようという流れになったんです。20周年の特別記念盤という感じですね。
そういう意味も込めての数量限定なんですね。20年前にリリースされた2枚も現在は入手困難ですが、今回『greedy dead souls』を手に入れましたのでお持ちしました。
玲央:わざわざ買ったんですか(笑)!? うちに2枚くらいありますよ。
晁直:僕は実家に置いてます。
葉月:僕、そもそも家にCDが1枚もないです。…これ、久々に見ましたけど写真の画質が粗いですね(笑)。あとスペシャルサンクスが面白い。
晁直さんちの愛猫ハナコちゃんのお名前も入っていますからね。
晁直:本当だ(笑)。バンドの知り合いがそんなにいなかったからかなぁ。
葉月:普通の友達の名前がめっちゃ書いてある。
晁直:ゆきのさん(サポートベース)のスペシャルサンクスまであるね(笑)。

当時はアルバム名も曲名も全て小文字でしたが、今回は全て大文字になっていますね。
葉月:これは最近の作品の流れに揃えた感じです。
玲央:昔の作品が小文字だったのは、僕が小文字の字面が好きだったから、というのが大きいんですよ。
バンド名も小文字ですものね。
玲央:そうそう。大文字って左右対称になる字が多いじゃないですか。当時は特に、左右対称じゃないアンバランスな感じの方が、デザイン的に気に入っていたんです。当時は今以上にこだわりが強かったのかなと思いますね。
葉月さんが、歌詞カードの見た目の美しさを気にされることに通じるものを感じます。
葉月:僕は、この頃はまだそういうこだわりはあまりなかったんですよ。そもそも、歌詞自体がかなり短かったですし、むしろ歌詞がない曲もありますし(笑)。
基本的に歌で表現したいことがないと明言していた葉月さんですが、それは今でも?
葉月:今はちゃんと意味を込めて歌って、それが刺さった時の破壊力を知ってしまったので、ある程度は意味を持たせるようになりました。しっかり狙っていかないと、手を抜いているみたいで嫌だなと思うようにもなりましたし。でも、この作品を作った頃は洋楽ばかり聴いていて、僕は英語ができるわけじゃなかったから何を言っているかわからなかったんですけど、当時はそれでいいんじゃないかと思っていたんですよ。歌を聴くときも、この人は歌詞で何を伝えたいんだろうということより、楽曲を含めた全体像で聴いていましたし。それで成立していたから、自分の作る曲も歌詞がなかったんですよね。
楽曲制作の変遷が見えますね。ところで今回、全て新録にしたのはなぜだったのでしょう?
玲央:今の体制もそうですし、演奏面のサウンドクオリティも、20年経つと圧倒的に上がっていると思って。そして、アレンジにほぼ手を加えていないというのもこだわりです。結成当初、10年20年と聴ける作品を作ろうと常々話していたんですけど、20年ぶりにほぼアレンジを加えていない状態で今の音で作品を作って、それが通用するのかという証明にもなるんじゃないかと。
20年ぶりの答え合わせはいかがでしたか?
玲央:立派だなと思いました。今聴いても時代に全く干渉されることなく、カッコいいなと思える楽曲揃いという印象があるので、すごいなと思います。
葉月:当時の歌は今とは全然違うんですけど、今回それをないがしろにはしたくなかったんですよ。今の俺はこうだぜ!って一新しちゃいたくなくて。なので、シャウトは当時の発声をかなり研究して録りました。未熟でできなかったことがいっぱいあったはずなので、今回はあの時こうしたかったんだろうなということをやろうと思って。
晁直:当時の作品も、これはこれで良い部分がたくさんあると思うんです。でもあの頃のlynch.は経験値が低かったから、理想はあってもできないことがいっぱいあったんですよ。だから、20年の経験を経て作った今回の作品で理想に近づけたというか。とは言え、当時の作品の方が好きという人も絶対いるだろうし、新しい作品の方が良いよというものでもないんです。なので、20周年の記念品みたいな感じで捉えてもらったらいいのかなと思ったりします。
10周年のアルバム『10th ANNIVERSARY 2004-2014 THE BEST』では、ドラムは「liberation chord」と「from the end」の2曲だけ録り直したそうですが、今回は?
晁直:今回は全部録りました。
玲央:僕も葉月も全部録っています。10周年の時は、ドラムは流用できるものは流用しましょうということになったので、当時使っていたレコスタにデータをもらいに行ったんですよ。ただ、以前使っていた二つのレコスタのうち、一つが廃業してしまっていて。救出できなかった部分は、晁直に新たに叩いてもらったんです。
むしろ、もう一つのレコスタに残っていたことに驚きました。
玲央:ですよね。しかもデータだと消えちゃうからって、メディアに残してくれていたんですよ。余談ですけど、その時にkeinとGULLETのデータもあるから渡すよと言われて、MOを渡されて(笑)。そのMOをどう処理していいかわからないんですよね。
MOというのが泣かせますね(笑)。今回、改めてレコーディングしてみて大変だった曲はありますか?
葉月:僕は歌詞がない曲です。なぜなら歌詞がないから(笑)。ライブでやる時は何も考えずに歌うとそれらしくなるんですけど、パッケージするとなると、ある程度は元の作品に近しくしないとなと思って。何度か元の歌をプレイバックしてもらって「何て言ってる?」って確認しながらやりました。
何て言っているか、謎は解けました?
葉月:解けたというか、聴こえたまま歌うしかなかったですね(笑)。でも自分の好きなように歌っていたから、一度聴いたら「あぁ!」ってなるんですよ。他のアーティストだとなかなかないレコーディングの方法かもしれないですけどね。
玲央:僕は、特に大変だと思うことはなかったです。大変って言ったら毎回そうではあるんですけど、それも面白いと思うし、好きでやっていることなので。ただ僕、レコーディングの時に異常に耳が冴えちゃうんですよね。自宅でラインを押さえて、東京に来てエンジニアと一緒にリアンプの作業をやるんですけど、ラインを押さえている時に微かに聞こえるエアコンのインバータノイズがすごく気になっちゃって。高周波のちょっとした音が許せなくて、結局アース線を引っ張って家の庭に鉄柱を刺して、アースを落としたりしていました。
通常のレコーディングでは耳にしない大規模な作業が…!
玲央:そうなんですよ。リアンプしてあの歪みでゲインを上げた時に、微かにいるやつが増幅されて浮き出てくるんです。それが「あれ、何かいるぞ…?」ってすごく気になっちゃって、もう完全にやっつけないと嫌だなぁと思ってしまいまして。
几帳面な玲央さんらしいエピソードです。
玲央:電線から200ボルト引っ張ればいいんですけど、工事を頼んだところにすぐ来てもらえるわけでもないので、父親と一緒に庭でハンマーを持って鉄柱を打っていました。自分の父親が第一種電気工事士の資格を持っているので、こういうことやりたいんだって相談して。色々ありましたが、録り自体は楽しくできました(笑)。
晁直:ライブでよくやる曲はライブのときに自由な感じで叩いちゃっているから、それをそのまま録音に落とし込むと、まぁ変なことになるんですよ。なので「PULSE_」とかは音源を聴きながら確認して、それを音源用のアレンジで叩いて…という作業でしたね。
やり慣れている曲にそんな作業が発生していたんですね。個人的に、ライブではレア曲の「らせん」の不思議なリズムのイントロが何か変化するのか気になっていました。
晁直:「らせん」は最初、基本的なリズム自体を変えようとしたんですよ。でも変えた状態で当ててみたらあんまり良くなくて。それで元のドラムに寄せたんですけど、改めて聴くと、何か変なんですよね。リズムがシャッフルなのにドラムが全然シャッフルしていないというか。それを昔、ディレクターにツッコまれたことがあって。その時初めて、確かに変だなと気づいたんですけど、でも成り立っているから僕はこれでいいんじゃないのかなと思っていたんです。そんな経緯もあったので、今回ちょっと変えてみようかなと思っていたんですけど、結果的に元の方が良かった、という感じでした(笑)。
これが「らせん」の正解なのかもしれませんね。それにしても、改めて20年前の音源と聴き比べてみて、葉月さんのヴォーカリストとしての劇的な変化を感じました。以前の作品は、率直に言うと喉を傷めそうでヒヤヒヤするというか。
葉月:ですよね。この時、自分の声が重くてリアルタイムで嫌でしたもん。それで玲央さんに先生を紹介してもらって、『underneath the skin』を録り終わってからボイストレーニングに通うようになったんです。自分の声が一旦嫌じゃなくなったのは、その次の『a grateful shit』(2006年7月リリースの会場限定シングル)を出した頃ですね。その時にはかなり声が軽くなっていました。
プルチェスト(地声を無理やり張り上げて発声している状態)から、最近は響かせることができるようになってきて、更に進化していますよね。
葉月:いやいや、まだまだですけどね。この頃は特にゴリゴリのプルチェストでしたから。ライブでの声の出方も今と全然違うんですけど、なぜかこの頃の曲はキーが高いんですよ。これはライブでは出ないだろ!という。当時どうしていたのかわからないですけど、キーは変えずにライブをやっていたから、かなり頑張って出していたんじゃないかな(笑)。
アルバムは自分たちの歴史の土台になるもの

Disc.3の『GOD ONLY KNOWS』も、ファン垂涎の曲が揃っていますね。
玲央:2005年4月~2007年1月の最初期という括りですね。一部、会場限定のものだったり、「無題」に関しては『enemy』(2006年12月リリースのシングル)初回盤ボーナストラックだったりします。
ここに収録されている曲たちも新録ですが、当時のご自身との違いは感じましたか?
葉月:『greedy dead souls』よりは感じなかったですね。やっぱり最初の作品だけに一番距離を感じるというか、ギャップがすごいんですよ。とはいえ、Disc.3でもギャップは感じました。僕は「A GRATEFUL SHIT」と「DIZZY」は元と聴き比べながら録ったんですけど、元のやつが粗いというか何というか…改めて聴いて「何でもうちょっとちゃんと録らなかったんだろう!」と思っちゃうくらい粗かったです(笑)。まぁそれがいいのかもしれないですけどね。
当時のご自身たちの中では、これが完成形だったわけですよね。
葉月:もちろん! 適当にやって粗いわけじゃなくて、頑張ってやっているんだけど粗かったんです。当時、口癖のように「何でもっとCDっぽくならねぇんだろう」って言っていたんですよ。歌唱でもミックスでもそうですけど、売れているアーティストのCDって、完成度が高いものが多いじゃないですか。なのに何で自分のは、ああいう風にならないのか疑問で。
原因は何だったんでしょう?
葉月:単純に下手だったんですよ。環境の影響ももちろんあったと思いますけど、シンプルに下手だからできなかった。でも、それが今回ではできていて、とてもCDっぽくて綺麗になりました。
特に「A GRATEFUL SHIT」でその言葉を実感しました。
葉月:そうなんですよ。ダミ声なんだけど、すごく聴きやすいですよね。
晁直:僕は、『greedy dead souls』を出したことで得たものが多いなと思っていて。それまでレコーディング経験がほぼない状態でlynch.を始めているから、『underneath the skin』以降は、レコーディングに臨む際の準備も含めて、この作品での経験を活かして臨んでいるんですよ。それを経て、『underneath the skin』から自分たちは変わり始めたのかなと思いますね。
葉月:デビュー作で、まだ何もわからなかったですからね。
玲央:アルバムって写真と一緒で記録なんですよね。その時に自分たちが考え得るベストを作れたらそれでいい。それを受けて次はどうして行こうという、自分たちの歴史の土台になるものだったりするんです。だから、過去の作品と今は距離があって当然だし、距離がなかったら進んでいないということになって問題だと思っています。そういった意味でも、あの頃に『greedy dead souls』という作品をリリースできて良かったなと。晁直も言っていた通り、それを受けて『underneath the skin』があるし、『underneath the skin』を受けてその後のシングルがある。本当に意味のあるアルバムだったなと思います。
バンドの黎明期を支え、今回リテイクされた楽曲たちを収めるジャケット写真は、アルバム『D.A.R.K.-In the name of evil-』(2015年10月リリース)同様、写真家の江隈麗志さんの作品ですが、葉月さんの奏艶の時に撮影されたものだそうですね。
葉月:どこかの壁を撮ったらしいですね。僕はそもそも江隈さんの写真ということすら知らなかったんですけど。
ジャケットを選ぶとき、そういう情報はない状態で決めるんですね。
葉月:そうなんです。デザイナーから「この中でどれがいいですか」と言われて、じゃあこれかな、と。でも今回のアルバムには2枚のアルバムが入っているから、ジャケットも2種類あるわけじゃないですか。だけど、世に出す時のジャケット写真は1枚にしないといけないわけですよ。それはまずいよねということになって。それで、どちらでもない何か別のものが必要じゃないかということになったんです。

玲央:象徴的なものではなく、もっと抽象的なものにしてもらいたいということになって。それで、いくつかいただいた案の中で、これが一番いいということになりました。
江隈さんの言葉通り、「2枚のアルバムを収める石櫃」に見事収まったという印象です。ところで、新曲「GOD ONLY KNOWS」はどの段階で作られたんでしょう?
葉月:実はこれ、元となる曲は2008年に作っていて、当時のツアーでもやっていたんですよ。
予想外のバックグラウンドが! その後ライブではやっていないんですか?
葉月:やっていないです。でも、2008年のアルバム『AMBIVALENT IDEAL』のツアー(TOUR’08「THE DIFFUSING IDEAL」)では毎公演やっていたので、当時のファンの方はこの曲を知っている人が多いと思います。2008年時点ではタイトルも歌詞もなくて、メディアには「新曲2」という曲名で出してもらっていました。歌詞は今年の2月に書いたんですけど、全然書けなくて泣きそうだったんですよ。
歌詞に苦戦したのは、元の曲を作った時期から時間的な乖離があったからですか?
葉月:いや、なかなかメロディーに合う言葉が出てこなくて、何にも書けない日々が1週間くらい続いていたんです。でも、このサビの〈死骸〉というワードが出てきて先が見え始めたんですけど、結局そこから2~3日はかかりましたね。10日間くらいずっと、ウーンって言っていた気がします。
このタイトルにしたのはなぜだったんでしょう?
葉月:これはこの曲がどうというより、20周年を記念してこの初期作を今、作っていること、そして20年もこのバンドを続けていることが単純にすごいと思うし、こういう未来を誰が予想できたんだろう、そしてこれからどうなっていくのかなぁということを思いつつ、この言葉になりました。
一瞬、LUNA SEAの「ROSIER」が浮かんでしまいましたが、関係なかったですね(笑)。
葉月:それ言いますよね~。確かに言われてみればなんですけど、違います(笑)。
それにしても、サビの後の〈DEAD?死ぬまで追うと言ったアンタ、どこへ消えた?〉のところを聴いて、2025年の葉月さんは遂にガチのラップを!と思っていたので、まさか昔の曲だとは思いもしませんでした。
葉月:遂にラップらしい感じでやりましたね。今までにも「THE FORBIDDEN DOOR」(2023年3月リリースのアルバム『REBORN』収録)とかでギリギリの感じで語りだった曲はあるんですけど、今回はもういいや!と思って(笑)。実際のところ、今まではちょっと遠慮していたというか、あえてやらないようにしていたんですよ。自分たちみたいな黒いバンドって、ラップとのギャップがあるじゃないですか。変に取り入れるとすごくダサくなる現象を僕はたくさん見てきたし、多分ファンの中にはそういうのが嫌いな人も多いと思うんですよね。
確かに相容れない部分があります。
葉月:そうなんですよ。だからずっと避けてきたんですけど、自分が好きで聴いている音楽の中にも当たり前のように出てくるし、lynch.としてもやったことがないから刺激になるだろうし、やりたいなと思って。それで、嫌がられないようにやろうとギリギリのところを突いていったらこういう感じになりました。
絶妙な分量で、スパイスとして効いている印象です。
葉月:本当はあの部分はただギターが鳴っているだけだったんですけど、最後の最後で何か入れてもいいかも、と思って。そこで、「ラップかぁ…ラップしかねぇか!」みたいな感じで入れました(笑)。
そこで「ラップしかねぇか!」という答えに辿り着いたところに、新たな葉月さんを感じます。
葉月:分量が少ないのもあって、挑戦するにはちょうどよかったんですよね。すごく新鮮でしたし。ラップって、メロディーと違って言いたいことが言いやすいんですよ。歌詞的にしなくていいというか、文章みたいな歌詞でも様になるというか。メロディーだとそれが邪魔になっちゃって、伝えたいことがあったとしても伝えにくいんですけど、そういう面でもすごく便利で、こりゃいいやという感じでしたね。
新しい武器を手に入れたわけですね。玲央さんはラップを聴いたときはどう思われました?
玲央:面白いことやってるなぁと思いました。僕は良い方向に捉えているんです。こういう周年のタイミングって、バンドの変化が受け入れられやすいオープンな年だと思うんですよ。だからこのタイミングでこういうものをやるっていうのは大いに結構ですし、さっき言っていたように、新しい武器を手に入れると来年以降も使えますからね。だから面白い面白い!って僕は手放しで喜んでいました(笑)。今やれることをやっておくと、来年以降はもっと自分たちのフィールドも広がるかなと思うので。
晁直:ドラム的には、内容はもう新曲という印象ですね。今回、葉月から来たデモ通り叩いているんですよ。節々に当時のフレーズは残っているんですけど、フィルとかもしっかり打ち込んでくれたので、当時のフレーズを忠実に再現したりして下手に変えるよりは、このままやろうと思って。