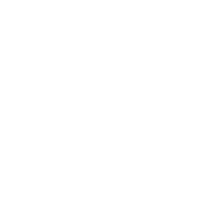清春がニューアルバム『UNDER THE SUN』で描き出す世界。“メロディーメーカー”として“表現者”として“一人の人間”としての清春の想いとは。
雅-MIYAVI-、TOKIE、キタダマキ(ex. Syrup 16g)、柏倉隆史(toe)、秋山隆彦(downy)、らの豪華ミュージシャンが多数参加し、アートワークでは“花人”赤井勝氏とのコラボレーションが実現した今作。それはもちろん作品として究極にかっこよく芸術的な一枚でありながら、今現在の清春のリアルな胸中が映し出されている。「ミュージシャンの憂鬱」、「生と死」…清春の口から語られた心の内。そして、間もなく迎える“20年目”への想いとは。
――今回のアルバムも聴けば聴くほどすごい作品だなと思いました。
清春:なかなかキャッチーですよね。
――「ALICE」と「MESSIAH」が収録されるのはわかっていたので、そういう雰囲気なのかなと思っていたんですけど、すごく幅が広かったです。
清春:確かに。後半が暗いというか重い感じだけど、前半はテンポいい感じ。
――今回多くのミュージシャンが参加されていますが、特に印象に残っていることはありますか?
清春:柏倉隆史くん(toe)と秋山隆彦くん(downy)は、今活躍されているドラマーなんですけど、僕的には初めて会ったので新発見でしたね。すーごいイイの見つけたって感じです(笑)。もちろん上手いっていうのと、今まで叩いてもらっていたドラマーとリズムに対する解釈が違ってて。タイプが違う感じ。
――どのような経緯でこのお二人が参加することに?
清春:秋山くんは三代さん(アレンジャー)が「すごく上手いと思いますよ」と。柏倉くんは元々ミュージシャンのデザイナーのところに洋服を見に行ったときに「誰か良いドラマー知らないですか?」って聞いたら、「toeのドラムの子、すごいんだよ」って。そこで曲を流しながら雑談してて「上手いっすね!」ということで。
――柏倉さんは意外なルートだったんですね。今作はギターのサウンドが際立っているものが多いですよね。「JUDIE」は雅-MIYAVI-さんとのセッションのような勢いのノリがすごくかっこいいですね。
清春:雅-MIYAVI-くんは何回か弾き倒して帰って行ったんですけど、サンプリングも入っているので若干整えて。そうやってオケをちゃんと作ってから歌ってるので、セッションではないんですよ。意外とちゃんとかっちり作ってる(笑)。
でも雅-MIYAVI-くんのフレーズをいじってるわけじゃなくて、まんまだけどね。ノリすごいよね。
――雅-MIYAVI-さんのギター録りはいかがでしたか?
清春:黒夢のライブに飛び入りしてもらったことがあるので、既に彼のプレイを目の前で見てるんですよね。なので、すごいのはわかってて。彼はレコーディングもライブで弾いてるのと変わらないですね。彼なりに変えてるんだとは思うんですけど、こっちからすると何もわからないくらい差がなくて。あれはきっと“ギター”というより“雅-MIYAVI-”っていうパートなんだよな。
ギターなんだけど飛び道具というか。
◆できないことの憂鬱じゃなくて、できてしまうことへの憂鬱
――個人的に「イエスタデイ」がすごく好きなんですけど、純粋な3拍子は清春さんには珍しいですよね?
清春:そうだね。あるにはあるんだけど、わかりやすい3拍子はなかったかもしれないね。
――現役引退を匂わせるような歌詞で胸が痛むのですが、どんな思いでこの歌詞を?
清春:日々思ってることですかね。作為的なことではなくて、根っこにここ数年はあるかなぁ。
思いとしては10年くらい前からあるかもしれないです。
――このタイミングでそれを歌詞にしようと思ったのはなぜですか?
清春:曲を作ってるときに、仮歌で既にそういう歌詞になっていましたね。
――最初に出てきた歌詞はどの部分ですか?
清春:〈残せないメロディ また降りてくる〉とか〈歌えなくなって 遥か切って Yesterday〉はほとんど変わってないです。
まだ引退はしないですけど、そういうときが来るんじゃないかなっていうのは当然根底にありますね。まだそれを歌えるだけ余裕はあるんですけどね(笑)。昔はどの曲を出しても記憶に残るような広まり方が成立するような時代で、そういう状況の中に僕もいたと思うんですよ。
20年弱経ち、作詞家作曲家として音楽的な才能が枯れるとかはまだ全く感じなくて、今回のアルバムもどの曲でもシングルで出せる自信はある。だけど音楽って自分が納得してかっこいいっていうのが一番なんですけど、聴く人がいないと話にならない。今はファンの人たちと楽しくやってますけど、徐々に淘汰されていくというか…まさにこの歌詞の感じなんですけど。引退したからどうこうっていうんじゃなくて、徐々にそういうふうになっていく感覚は、続けていたとしてもあるっていうことなんですよね。ミュージシャンを永遠にやるとしたら、そういうことになり得ますよね。もし僕が不死身の体で永遠に死ななくて音楽を続けていたとしたら、当然ファンの人の方が先にいなくなる。聴く人がいなくなる、でも曲はどんどんできちゃうんだっていう感覚。
――聴く人がいなくなる…。
清春:聴く人がいなくなってもできる気がするんですよ。今40代だけど、曲作りだけならあと20年くらいは余裕でできると思うんだよね。「曲ができないなー」って困ったことがないから。そういうメロディーメーカーとしての憂鬱というか。できないことの憂鬱じゃなくて、できてしまうことへの憂鬱。
すごく良い曲なのに誰かに聴かれなかったら、報われない。そんな感じするんだよね、最近。
だから逆にしょうもない曲でもいいんじゃないかなって思ったりもする(笑)。
とはいえ、作曲という部分でのプライドというか、自分のレベルはわかってるので、しょうもない曲は正直できないですね。
これは長くやってるミュージシャンの憂鬱だと思います。
――なるほど…。
◆生は死に近いのかな
――ところで、「UNDER THE SUN」はメロがすごく難しいですね。
清春:頭からめっちゃ高いんですよ。三代さん、キー設定は大丈夫だったのかな?っていう(笑)。それくらい高くて、まず驚きましたね。
――(笑)。原曲の時点ではこんなに高くなかったんですか?
清春:半音階上がってますね。これはずーっと続くと辛いっていうキー設定なんですよ。バコーンッて高いところがずーっと続いてて、その付近を行ったり来たりしてるくらいの高さで構成されているので、オケを録っちゃってから「えっ?」て驚くっていう。この歌入れに関しては、上手く歌えるか歌えないかっていうより、高さが出るか出ないかっていうとこに終始しましたね。
――清春さんの歌詞に“母の子宮”というワードが出てくるとは思いませんでした。
清春:地球の周りを太陽や月が回ってるように、自分の命が球体で自分の周りをゆっくり回って進んでいく…そういうことをイメージして歌詞を書いていたんですよね。生きる死ぬとかではなくて、単純に生命体が日々ゆっくり回ってるという。命の流れを生きてることを実感できるような、息を吸って酸素が体に送られて血液が運ばれて心臓が動いて…当たり前なんだけど…上手く言えないですね(苦笑)。
――この歌詞に出てくる瑠璃蝶草は「the sun」の歌詞にあるロベリアの和名なんですね。なぜここに入れようと?
清春:誕生花なんですけど、瑠璃蝶草は“蝶”が入ってるし、この曲はワードとしては自分で自分のことを歌ってる部分があって。〈春を舞って〉の“春”もあるし、〈母の子宮〉も完全に自分の母を想像してました。そもそも自分はどこから来たのかっていう。死ぬことはわからないので、どこから来たかっていうことを想像した方が死ぬことに近いのかなと思って。死ぬってことは未来だけど、生まれてきたってことは過去だから、覚えてるかもしれないじゃないですか。手掛かりはどの人もお母さんにあるんだけど、赤ちゃんのときだから覚えてない。だから生は死に近いのかな。結局答えはなくて。単純に生命体がゆっくりゆっくり回ってる、それぐらいしか事実はない。どこから来たのかわからないし、どこに行くのかもわからない。だけど今ぐるぐる回ってるっていう…最近はこれがテーマですかね。
――ふとした瞬間に「なんで生きているんだろう?」とか「どこから来たんだろう?」って漠然と考えることってありますよね。
清春:あるよね。よく思ってたのが「なんでたまたま俺になったんだろう?」っていう。もしかしたら日本人じゃなかったかもしれないし、日本人でも「なんでこの体とこの顔の中に入ったんだろう?」とか。本当は当然そういう順番じゃないんだけど、与えられたロボットみたいなものの中に僕っていう魂が入って、責任を持ってこの体と一緒に過ごしてる感じ…ないですか(笑)?
――わかります。中身(魂)と容れ物(体)は別々なんじゃないかっていう感覚。
清春:密接な関係はあるんだけどね。ケガをしたら自分が痛いわけだし。たまたまこの“森清治さん”の体に入っちゃって、気が付けば自分だったんだけど、もしかしたら死んだときに次に違う体に入って「は!」って気付くかもしれないって思っちゃうんですよね。初めから自分であるのが当たり前っていう前提で生きてるんじゃなくて。疑問ですよね。街を歩いていたら、いろいろな人がいるわけじゃないですか。なんで俺たまたまあの人にならなかったんだろう? あの犬じゃなかったんだろう?って(笑)。自分に対して「俺で良かった」って思えるときもあるし。俺は一回この体に入っちゃったから、この体が滅びるまでは出られないっていう。そういうこと考えるときない?
――よく考えていましたね。なんなんだろう?って。
清春:俺はすごく考えてた派なんだよね。だんだん歳をとっていくと肉体と魂が重なっていく度合いが高くなるんだと思うんですよね。子どものうちは結構離れてるの。もしかしたら最終的に死ぬ間際にまた離れていくのかもしれないけど。体がだめになる感覚って出ると思うから。僕の持論だけどね(笑)。
◆すごく優雅で芸術的で圧倒的でした
――この「UNDER THE SUN」のPVなど、今作のアートワークで“花人” (フラワーデザイナー)赤井勝さんとのコラボレーションが実現した経緯を教えてください。
清春:先輩から食事に誘ってもらってお会いしたのが最初ですね。ミュージシャン以外で自分がやってること、やりたいことを言葉で言える人と話す機会って僕らはあまりないじゃないですか。先生は装花をしている理由というのが明確にあって。すごく言ってることに無理がない、こじつけじゃないんですよね。花って形があるものじゃないですか。音楽って耳に入ってきて感じることはできるけど、手に取れないでしょ。花は枯れていく儚さはあるし、絵は枯れない…表現の中にはいろいろなパターンや良し悪しがあると思うんです。花に音はない。動かないし喋らない。音楽には目に映るものはない。…そんな話をずっとしていたわけよ(笑)。でも先生は「音楽には空気を振わすっていう部分で、思い次第ではすごく人の心を包み込むようなムードを奏でられるし、素晴らしいじゃないですか。僕らの花には音楽がないので、無音の中で匂いとかそのもの自体に生命を感じられるっていうリアリティはあるんですけどね」って。なぜ花を生けるのか、花を飾るのか。「共有スペースやパーティーに花を添えるのは、場所に花を添えてるわけじゃなくて、それを見た人の心に花を添えるんですよ」って。そういうとこでは音楽も花も近いですよねっていう話を…永遠にしてたんです(笑)。負けそうでした(笑)。
――ジャンルは違うけど、同じ表現者として意気投合したんですね。
清春:で、一緒にいた先輩が「清春のPVとか何かやってもらったらいいじゃん」と。最初はお互い謙遜し合って(笑)。でも、やってもらいたいなっていう気持ちはありました。人間って真っ当じゃない部分は誰しもあると思うんですけど、先生と話してみて、正しい部分が正しくちゃんとあるという感じがしたんですよね。完璧じゃないにしろ、正しく生きようとしてる部分っていうのが特に明確にある方という印象。偽善的にやってるんじゃなくて、花で何かを飾っていきたいという…僕とは違う感覚なので上手く説明できないですけど。何回か会ううちにすぐに話が決まりましたね。
――完成したアートワークを見て、いかがでしたか?
清春:人生の経験として、新しいチャレンジができて良かったですね。ジャケット写真や映像って徐々に同じになっちゃうんですよ。例えば自分が気に入ってるカメラマンが三人いるとするよね。三人で回していくと、何年か後には絶対同じになるんですよ。一人にしか撮らせない人もいるじゃない? 僕もその時期に気に入ってる人に撮ってもらうこともあるんだけど、そうしていくと世の中にはその人から見える自分の顔しかないんですよ。カメラマンとデザイナーがいて、スタジオ、照明、衣装があって…だいたい一緒になっちゃうんですよね。他の人のジャケ写やPVを見て「あ、ここ行ったことある」とか。それを繰り返していくと新しいものへの興味や欲求がどんどん増えていって、じゃあ海外行きましょうっていう話になるわけですよ。撮ったことのない写真や映像をとなると。でも、僕らがデビューした頃はバブルだったから海外は普通にあったんですけど、今はなかなかないわけで。だから今回のはここ何年かで本当に久しぶりにやったことのないことをやれたっていう感じ。しかも、すごく優雅で芸術的で圧倒的でしたね、この現場は。素敵な体験でした。
――清春さんの楽曲は歌詞やタイトルに花の名前がよく出てきますよね。
清春:ずっとあるよね。ソロになってから特に多いよね。
――赤井さんとの出会いは必然だったのかもしれないですね。
清春:“清春”っていう季節のワードが先生的に良かったのかもしれないなと、勝手に思ってます(笑)。
――なるほど(笑)。さて、10月30日にお誕生日を迎えられ、今作のリリース時には44歳になっているわけですが、これから45歳を迎えるまでの一年の抱負をお願いします。
清春:あー嫌だなー! 45歳になって46歳になって…もう50歳じゃないですか(笑)。
もし50代になったときに、このジャンルでこの環境の中でやってたとしたら、それも立派だとは思う。
バンドから一人になり来年10年目になって、黒夢とsadsでやってきた10年間に追いつくわけです。15年のときは黒夢5年、sads5年、ソロ5年だったんだけど、20年になったらバンド10年、ソロ10年ということになりまして。44歳から45歳ということよりは、その中の一度しかない貴重な1年。トータルしたら来年20年目になるんだけど、自分の歴史、やってきたことを今のキャリアも含めて整理していくこの1、2年っていう気がするんですよね。20周年っていうのは黒夢でデビューしてから20年なわけだけど、黒夢にしてもsadsにしても“20周年”ではないんですよね。
なぜなら20回“周って”ないから。“周ってる”としたら僕でしかないよねってとこで“清春”にしかならないんだろうなと。そこに黒夢とsadsの歴史も含まれるというキャリアになってきた。それが外に向けても説得力のある年数になっていくのかなという感じですかね。僕にとってはバンドは鎧。鎧を着たり脱いだりして…結局それは“清春”なのかなって。気負いはなくて。陸上のランナーのゴールテープに自分から向かっていくんじゃなく、あれが勝手に来る感覚なんですよね。そのゴールの紐を切るということは切る前よりも向こう側に行くわけなので、切るときには向こう側がもう見えてるわけじゃん。見えてるんだけど線がある。そういう感覚。だけど切る前と切った後では、嬉しさはあるんだろうけど、きっと何も変わらないんだと思うんだよね。未知の世界という感じはしないです。20年目、21年目の“清春”がもう見えてる感じはある。バンドを復活させたことによって、黒夢やsadsに僕が含まれるんじゃなくて、より清春の中に黒夢、sadsが含まれていくっていう感覚が強くて。それを自分の中で整理する時期なんじゃないかな。
(文・金多賀歩美)
清春
<プロフィール>
1994年、黒夢のヴォーカリストとしてデビュー。1999年に黒夢は無期限の活動休止。同年、sadsを結成しデビュー。2003年に活動を休止。同年、ソロアーティストとしてデビュー。2010年には黒夢とsadsの活動を再開させ、現在は黒夢、sads、ソロアーティストとしての活動を並行して行っている。2012年、シングル『流星/the sun』、『涙が溢れる/sari』を発表し、11月7日にはニューアルバム『UNDER THE SUN』をリリース。2013年1月から全国ツアーが決定している。また、2012年7月~12月「MONTHLY PLUGLESS」と題したアコースティックライブを毎月数公演開催中。
■オフィシャルサイト
http://www.kiyoharu.jp/
『UNDER THE SUN』
2012年11月7日発売
(avex trax)
清春、約3年ぶりのニューアルバム。豪華ミュージシャンが多数参加&“花人”赤井勝氏とのアートワークコラボレーションが実現した至極の一枚。
【収録曲】
[CD]
01. WALK ON THE MOON
02. JUDIE
03. LAW’S -New Take-
04. イエスタデイ
05. the sun -album version-
06. 流星
07. ベロニカ
08. 涙が溢れる
09. ALICE
10. MESSIAH
11. UNDER THE SUN
Bonus Track. FLORA ※CD ONLYのみ
[DVD]※初回限定盤
・FILM UNDER THE SUN
・the sun【MUSIC VIDEO】
・流星-album version-【MUSIC VIDEO】
・LAW’S-album version-【MUSIC VIDEO】
・涙が溢れる【MUSIC VIDEO】
・sari【MUSIC VIDEO】
・UNDER THE SUN【MUSIC VIDEO】
[Extra Picture]※初回限定盤
the sun【commercial ver.】