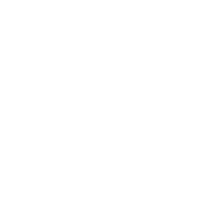2017.10.8
DEZERT@中野サンプラザ
「DEZERT LIVE TOUR “千秋を救うツアー 2”」

救いとは何なのか。救済とは何なのか。天下のWikipediaセンセイによると、それは【好ましくない状態を改善して、望ましい状態へと変える(達する)ことを意味する】のだという。
では、ここからが本題だ。今春に行われた[千秋を救うツアー]を経たDEZERTが、再び8月より開始していた[千秋を救うツアー2]の千秋楽・中野サンプラザ公演。この場において、フロントマンである千秋が集った聴衆に対し、アンコールの締めくくりとして「「ピクトグラムさん」」を歌い出す前に、ある種の結論として述べた言葉。今回のレポートに関しては、敢えてまず最初にそれを明記することとしたい。

「キレイゴトを言うつもりは無いですけど、このツアーをやって確信出来たことがひとつあります。それは…僕が生きる理由でもあるけど、この僕の手が何処まで届くかどうか。誰に触れるかどうか。ただそれだけを、ただそれだけを求めて。ここから生きていきたいと思います。だからもし、積み上げてきたものが崩れ去ってしまっても。また、僕らと君とで遊びませんか。この手が、どこまで伸びるかどうか。大きさじゃなくて、場所でもなくて。この汚ねぇ声が、どこまで届くかどうか。それが一番大事なんです!」
吐き出すように、叫ぶように語られたこの言葉の持つ意味。これは、昨今のDEZERTのことを語ろうとするならば、必要不可欠なものだと言えるはずだ。何故なら、今回の[千秋を救うツアー2]が始まる直前、彼はとある取材に際し以下のような物言いをしていたのである。
「僕は、ステージに立っているときに何時も虚しくて。だけど、去年あるときに思ったんですよ。考え方を変えたら、俺も不特定多数の人に向けて無の境地になれるのかなって。そうすれば、俺も少しは救われるのかなって。でも、やっぱダメでした。[千秋を救うツアー]の途中で「無理だ、俺」となっちゃって。だからもう、俺は誰かを救うとかそういうのはヤメにしたんです。今度の[千秋を救うツアー2]っていうツアータイトルも、別に意味なんてありません。時期が迫ってきて決めなきゃいけなくなって、メンドウだから単に2ってしただけ」

半ば“投げやり”にも感じられた、この言葉そのままに。今思うと、[千秋を救うツアー2]の初日を飾った8月の恵比寿LIQUID ROOM公演は、良くも悪くも必死にあがき・もがきながら自己解放を図ろうとする千秋の姿と、そんな彼を寛容に受け止めバックアップしようとする楽器隊の頼もしい様子が、くっきりと浮き彫りになっていたような印象があったのだが…あれから約2ヵ月が経過して、事態は随分と変容していた。
何故なら。不穏かつアンニュイな憂鬱さを漂わせながらも、やけに肉感的で躍動する音像に溢れた「おはよう」。来たる10月25日に発売が予定されている、DEZERT初となるシングルのタイトルチューン「幸福のメロディー」。冒頭にてこれら2曲を見聴きしただけでも、DEZERTが夏に観たときとは既に違う次元でライヴパフォーマンスを行っている、ということが明白だったからだ。

当然ながら、DEZERTならではな良い意味での歪(いびつ)な部分はしっかりと残しつつも、ライヴバンドとして一丸となっている様や、自然体で自己解放へと向かう千秋の伸び伸びとした姿から、成長と変化を感じたのは何も筆者だけではあるまい。
それでいて、何時も通りに変わらないところは歴然としてあり、熱を帯びた音の渦を次々と生み出すバンド側と、それに呼応するかたちで激しくアタマを振り回しながらカラダを揺らす観客たちの姿は、DEZERTとしての至って通常運行モードであった、とも言えるはず。つまり、彼らにとってこの中野サンプラザ公演は本来であれば“初の全席指定制ホールワンマン”だったことになるものの、その事実は最初から隅へと追いやられてしまっていたというわけだ。なんと贅沢にして、大胆不敵な話だろう。

実際のところ、ダイナミックなロックチューン「大塚ヘッドロック」などを始めとして、何曲かでは1階席において俗にいう横モッシュが盛大に繰り広げられたほか、2階席でも飛び跳ねるオーディエンスたちの動きと連動して、床がバウンドするように振動するという事象が勃発。
ホールらしい大掛かりな特効や、派手な演出などは見受けられず、ライティングについても何時も通りピンスポットを排除して明度よりも彩度を重視した場面づくりがなされていた今回のライヴについては、あくまでもバンドとファンによって生み出される空間そのものをリアルに堪能したい・堪能して欲しい、というDEZERTなりの強いこだわりが端々から感じられたのは間違いなく、その効果は最大限に発揮されていたと言っていい。

なお、とかくDEZERTと言えば千秋の発する冴えた毒舌やら、異端なほどに刺々しいバンドとしてのイメージが先行しがちなところもありはするだろうが、いざその世界へ足を踏み入れてみれば、決してソレだけではないところが多々あることも、筆者としては忘れずに伝えておきたいところ。
たとえば、このたびのライヴにて本編中盤に演奏された「「軽蔑」」は、曲調やその演奏内容だけを聴いていれば、なんならロキノン系が好きな人々にも響くのではないか?と思えるような面持ちを持っている1曲だ。
タイトなうえに疾走感をもたたえたSORAのドラミング、軽快にドライヴする中で抜群の安定感をみせるSacchanの指弾きベース、精緻にしてエモーショナルなプレイで曲を彩ってゆくMiyakoのギターワーク、シャウトは一旦オアズケにしながら切々とした詞世界を美しく綴り上げる千秋の歌。この4つのファクターによって織りなされる音楽には、普遍性と説得力があるとこれまた断言出来る。

むろん、どこからどうやって見てもDEZERTがヴィジュアル系に属するバンドであることは厳然たる真実であり、彼ら自身がヴィジュアル系と名乗ることに対しての誇りを持っていることもまず間違いないが、一般的に長くはびこり続けてきた「V系ってどうせ見た目だけで、音なんか所詮はコケオドシ的なモノなんでしょ」的なありがちすぎる既成概念だけは、DEZERTにはおおよそ当てはまらない。
それゆえ、V系の中でもDEZERTはハミ出しっ子になりがちなところもあるが、逆に言えばアーティストたるものハミ出してナンボ。そういった意味では、この夜の本編終盤にて巻き起こった一幕は彼らの持つ特性を端的に表しいていた、とも言えそうだ。

「…なんか、ホールって別に良いところだとは思えません。もう、僕は我慢出来ないんだ。ルールなんてクソくらえ、などとは言うけれども、もちろんルールは大事です。(中略)でも、アブナイことしよっか? 全責任は、主催者であるイベンターが取る(笑)。蹴散らそうか! 何を? 何でもいいさ。さぁ、どうするオマエら。好きなようにやってみろ。ただし、飛ぶなよ!!」
その名も「「変態」」なる楽曲の演奏を始めるのにあたり、千秋がこう煽った途端。待っていましたとばかり、自席を離れた観衆たちが堰を切ったような勢いをみせながら、ステージ前へと大集結。
警備スタッフのみならず、舞台まわりのスタッフまでもが揃って慌てふためく中、威風堂々とライヴハウスと見まごうような白兵戦的パフォーマンスを見せつけたDEZERTと、DEZERTを支持する人々の発していたヴァイブスは熾烈にして鮮烈だった、と言うほかない。

一転して、興奮冷めやらぬ中でのアンコールでは、このライヴ当日に無料配布された「おやすみ」が安らかな雰囲気を生み出していたところも秀逸であり、そこからの「「遺書。」」から「「切断」」、さらに締めの「「ピクトグラムさん」」へと続いた怒濤の流れも圧巻でしかなく、DEZERTの真骨頂はここに極まれりといった風情であったのだが。ここで最後に、千秋が残した言葉も実に印象的なものだった。
「生きてるか!俺も生きてるよ。こんなバンドが好きな、普通でない人たち!これからもっと、嫌われていきましょう。そして、自分を好きになりましょう!!」
救いとは何なのか。救済とは何なのか。その疑問に対するひとつの回答は、言うなればこの夜のライヴそのものであったのかもしれない。ここに来て真理に近い答えを得た彼らの行く末は、まさに未知数だ。生きる理由を再確認した、千秋とDEZERTが次に踏み出すあらたな一歩に幸多からんことを。



(文・杉江由紀/写真・西槇太一)
DEZERT オフィシャルサイト http://www.dezert.jp